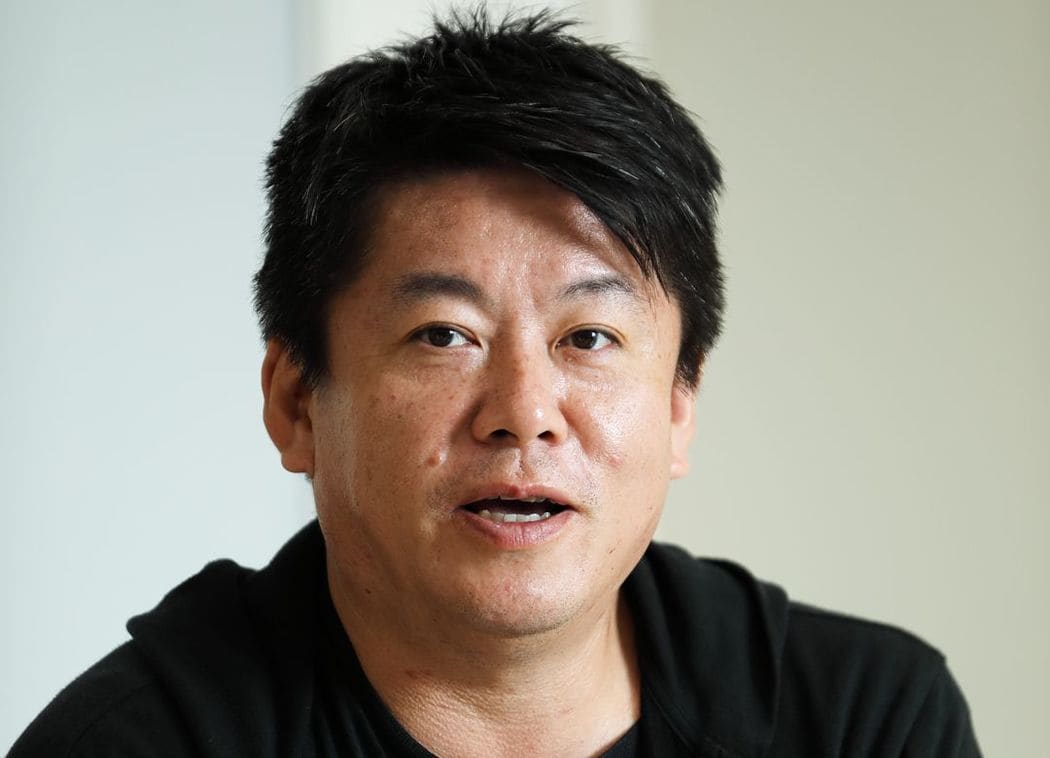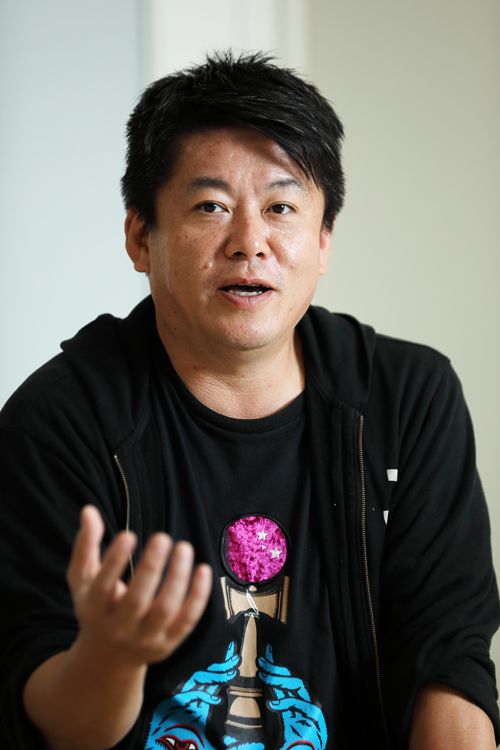※本稿は、堀江貴文『僕たちはもう働かなくていい』(小学館新書)の一部を再編集したものです。
AI研究は「身体性」にフェーズが移っている
AIが人間に近い「手」を持ったとき、ディープラーニングの進化は、とてつもない大ジャンプを遂げる──。
私たちの幼児期を思い出してみれば、明らかだ。世界の情報を得るための一番のツールは、何だっただろう?
言うまでもなく、「手」だ。母親に抱きつく、食欲を満たすために物をつかんで食べる、ケガをしたところを撫でる、文字を学ぶのに鉛筆を持つ、気になったものを拾って見る……生きていくのに大事な知識や、経験を積み重ねていくのに、「手」は欠かせなかった。
「手」を介した無限のインタラクションが、知性を養った。さらに言うなら、「手」のインタラクションで、人は、知性体として成長できたと言えよう。
誤解されてはいけないが、生まれつき「手」がない人は、知性体に劣るという意味ではない。「手」がない人は親や介護者の協力を得て、「額」や「胸」や「足」など、「手」の代用となる器官で、生きていくための情報を蓄積している。「手」そのものが大事というより、知覚・感触によって得られる、身体性を通過したビッグデータが、進化には重要だという話だ。
AI研究は、「身体性」の開発にフェーズが移行しようとしている。ただし開発は容易ではない。例えば、「手」は紙のページをめくる繊細さ、一定の重さのものを傷つけずに運ぶ力加減、熱いものを触ったら引っ込める察知力、かゆいところを丁度いい具合にポリポリと掻くなど、複雑な機能の連動を5本指で処理できる。
日本は「手」の開発で世界をリードできる
そんな超高性能ツールを人工的につくりだすのは、莫大な予算と人材と施設が必要だ。
そこまで高性能でなくても、世界とのインタラクションをある程度までクリアできる「手」の創造は、いち早く実現させねばならない。
日本のAI研究のトップランナーのひとり、東京大学大学院特任准教授の松尾豊さんによれば、世界中のロボット研究者たちも、「手」の開発に着目しているけれど、進展は鈍いそうだ。特に欧米では宗教的な問題で、人間に寄せた形状のロボットをつくることに、いまでも抵抗があるという。
その点、日本なら問題はない。多くのロボット研究の書物で語られているように、『鉄腕アトム』『サイボーグ009』『ドラえもん』など戦後のSFコミックの浸透で、ロボットへの親和性が世界一高いと言える。
世界のなかでも際だって、ビジネスや生活に、ロボットを立ち入らせることに抵抗が薄い国民性だ。精巧で人間そっくりの「手」を、たやすくロボットにくっつけられると思う。
ビジネス的な観点から見ても、「手」の開発においては、日本が世界のどこよりもリードを取れるチャンスは大きい。
「GAFA(G=グーグル、A=アップル、F=フェイスブック、A=アマゾン)」によって牛耳られたテクノロジーの世界地図を、塗り替えることすらできるかもしれないキーテクノロジーであるはずだ。