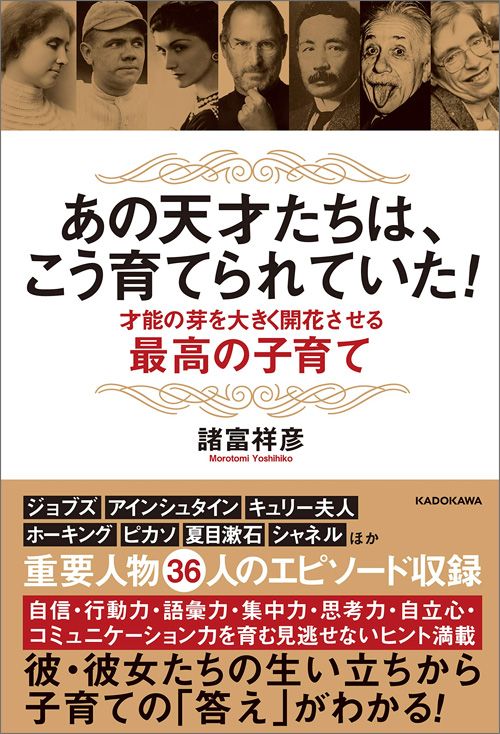学費だけは出してくれた父親
漱石のこの言葉からは、世間に対する冷めた感情を読み取ることができます。彼の上にはたくさんの兄姉がいましたが、姉たちは母が異なり、兄たちも歳が離れています。自分に親身になってくれる人は、実家には誰もいませんでした。でも唯一、母だけは漱石のことを温かく見守ってくれていたようで、後年まで、彼は母の優しさを脳裏に刻んでいたといいます。
その母は、1881(明治14)年、55歳で亡くなりました。漱石が14歳のときのことでした。
ではその後、自分に「愛情」を示してくれていた母親を失った漱石が、道を外した人生を送っていたのかといえば、そんなことはありませんでした。文学の道を志す彼の同行者となったのは、東京大学予備門予科に入学した後に出会った友人たちであり、実父でした。実父は、漱石が家に戻ってきたことは歓迎していなかったようですが、夏目家としての世間体も少なからずあったのかもしれません、学問を修めるためにかかる費用については出資してくれていたようです。
バンカラな友人たちとの交流で立ち直る
当時の予備門の学生は、いまでいえば17、18歳の青年。けっして大人とはいえない生意気な年頃です。しかし、そんなバンカラな友人たちとの交流で、「親の愛」を十分得られずに育った漱石の“心のすき間”が埋まり、勉強にも集中できるようになったのでした。ただ、ずっと首席で通していたという漱石が2年に上がるときに落第したことも、彼自身に大きな衝撃を与えたようで、漱石はのちの作品の中でこう振り返っています。
「もしその時落第せず、ただ誤魔化してばかり通ってきたら今ごろはどんな者になっていたか知れないと思う」(『落第』)
漱石は、友人たちとの交わりを通じて素直な性格に“立ち直った”頃、友人・米山保三郎のアドバイスによって文学の道を志すようになり、彼らと同じく予備門で学んでいた正岡子規(本名・常規)とは、まさに親友と呼べるような付き合いをすることになるのです。