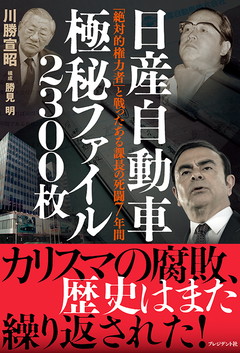1年間続いた“座敷牢”での日々
以前、豪州日産の社長を務めていたとき、取材のため訪ねてきた新聞記者との間で自動車労連会長の話題になった。塩路一郎について若いころから知っていた古川さんは、何気なく、「あれはたいした人物ではありませんよ」と漏らした。ここから予想外の事態が始まる。
まもなく、豪州日産社長の職を解かれ、帰国命令が下った。
日本で待っていたのは、「人事部付」の辞令と人事部の部屋に置かれた机1つだった。仕事はいっさい与えられない。朝出社しても、誰からも声もかけられない。「ひと言も口を利くな」と部内で指示が出されていた。
何をするともなく時間だけが経過し、夕方になると退社する。やがて、精神状態が不安定になったのか、帰宅後、テーブルの角に額をガンガンと繰り返しぶつけ、血が流れてもぶつけ続けた。それはまるで自らの命を絶とうとしているかのようだった。
「そういう主人の姿を私は見ているんです。組合に刃向かうなど、お願いですからやめてください」
「いえ、もうやると決めました」
夫妻から必死の説得を受けても応じるわけにはいかなかった。夜も更けて終電もなくなり、その晩は泊めていただいた。
翌朝のことだ。
「これをあとで読んでください。誰にも見せたことがないけれど、あなたには渡しておきたい」
ご自宅を辞するとき、古川さんから、当時書いたという手記を託された。そこには、1年間も続いた“座敷牢”のような日々の壮絶な記録が、400字詰め原稿用紙16枚に手書き文字でぎっしりとつづられていた。
部下もなく、仕事もなく、書類もなく
手記は、机1つだけを与えられた早春のころの回想から始まる。
晴れた日には太陽の日射しがまぶしく私の沈む気持を鋭く奥底まで射し通した。明るい他人の笑顔が何故かうつろに遠くこだまし、人生に喜びも笑いも何処にも見当たらぬような目まいで、ボーッとした。
雨の日は、泣くに泣けない気持が往きも帰りも会社通いの重い足を、更に重くした。坐った会社の席での雨の一日は殊に長く、近くのビルの屋上に叩きつけられる雨足を飽きずに物悲しく眺めていた。
エリートコースの豪州日産社長から、一転、座敷牢の日々を強いられ、魂の抜け殻になった。それが、オーストラリアで古川さんが発したひと言を知った塩路一郎による報復だったことは、手記のなかで人事担当役員から聞いた話として示されている。精神的ストレスから胃潰瘍になり、足もしびれるなど、身体的にも異変が生じるようになり、通院しているうちに夏も終わった。
手記の記述は秋へと移る。古川さんは、人事担当役員から、日産を離れ、群馬県の小さな町にある、従業員40人のプラスチックメーカーの役員として出る案を提示された。
古川さんは長く従事した営業販売関係の仕事を希望したが、塩路一郎の意向により、自動車労連傘下の労組がある企業、すなわち、日産圏の販売会社などへ転じることはできないこと、そのプラスチックメーカーであれば、日産圏外なので、了解が得られたことが伝えられた。
それでも一縷の望みを抱いて面会を申し込んだ川又会長(当時)からも、こう言い渡されるのだ。