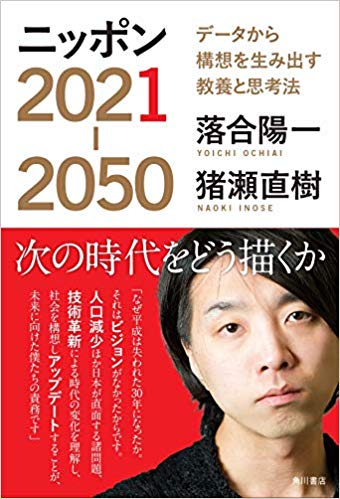採用条件は「何かひとつでも落合陽一に勝てるものがある」
――猪瀬さんは落合さんの人柄にも強く惹かれているそうですね。
山本五十六の言葉にあったように「褒めてやらねば 人は動かじ」という点を理解しているのだと思います。眼差しがすごく優しい。多少厳しいこと言っても、それを包み込むような本質的な優しさがあります。特に学生からはすごく慕われているようですね。
彼は自分の研究室で学生や研究者を採るときの条件の一つとして「何かひとつでも落合陽一に勝てるものがあること」を挙げていると聞きました。それは「バトミントンがうまい」といったことでもいい。何かひとつ誇りを持てる長所があることで、自負を持ってコミュニティに参加できることが大事だ、と。
それはダイバーシティ(多様性)と言い換えることもできるかもしれません。多様性とは「誰でもただ平等に扱う」ということではありません。それぞれの違いを認識し、その違いに敬意を持つことが重要なのです。
落合くんはオーケストラと組んで「耳で聴かない音楽会」を開いています。耳が聞こえない人でも音楽会を楽しめるように、光や振動でオーケストラを再現しようと試みていました。僕はその発展形である「変態する音楽会」のチケットを買って観に行きました。「楽器」のひとつとして映像が「演奏する」というもので新鮮な体験でした。
いまの日本社会に2021年以後のビジョンがない
――落合さんとの共著を出すことになったきっかけは?
落合くんとの出会いは2016年の年末でした。たまたま特急列車の席が近くて声をかけてくれたのです。そこから折に触れて対談する機会があり、彼がアーティストであると同時にテクノロジーを使って社会をよくするために動き回っている本当の働き者であること、そして近代の行き詰まりという問題意識を共有していることがわかりました。そこで「じっくり日本の近代について一緒に考えないか」といって誘ったのです。
僕は常々、日本の近代の行き詰まりを打破したいと考えてきました。それは「ムダ」(非効率)と「ムラ」(利益集団)という言葉に象徴されます。落合くんは同じ問題意識をもつだけでなく、いまの日本社会に2021年以後のビジョンがないことを危惧していました。
未来を描くには現在がどのようにできあがってきたかを知ることが不可欠です。そのため共著では、僕が日本の「近代」の構造と自分自身が取り組んできたものを示し、落合くんがデータやテクノロジーの動向から未来のビジョンを示す。それらを通じて、近代を乗り越え、未来を創るための発想や生き方のヒントになる本になればと考えました。