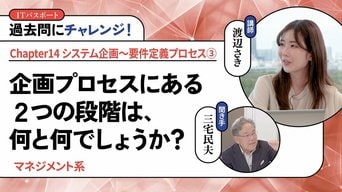「がむしゃら」から「顧客志向」へ

アサヒビール社長 荻田伍●おぎた・ひとし
1942年、福岡県生まれ。65年九州大学経済学部卒業、アサヒビール入社。89年長野支店長、95年福岡支店長、97年九州地区本部長、2000年常務。02年アサヒ飲料副社長、03年同社社長。06年より現職。出向先のアサヒ飲料では赤字体質を脱却しV字回復に導く。子会社からの社長就任は前例のない抜擢だった。
1942年、福岡県生まれ。65年九州大学経済学部卒業、アサヒビール入社。89年長野支店長、95年福岡支店長、97年九州地区本部長、2000年常務。02年アサヒ飲料副社長、03年同社社長。06年より現職。出向先のアサヒ飲料では赤字体質を脱却しV字回復に導く。子会社からの社長就任は前例のない抜擢だった。
1980年代初め、40歳になるころだ。仙台支店で、営業担当の課長を務めていた。課員たちが顔をそろえるのは、毎週月曜日朝の会議のときだけ。あとの日は、全員が担当地域を巡回する。自分も、管内を回り、各地で夜をすごす。そして、翌朝6時、ビジネスホテルや旅館にある公衆電話の前に立つ。手に、10円玉があふれていた。
部下たちの宿泊先に、次々に電話を入れる。泊まった部屋から交換台を通すと、いったん切って待つケースが多かった。もどかしい。電話に部下が出ると、まず「元気か?」の言葉が出る。アサヒビール(当時の社名は朝日麦酒)の国内シェアは10.7%と、入社時の半分以下になっていた。しかし、「できたか?」とか「やったか?」といった営業の成果を問う話はしない。ねぎらい、励まし、悩みを聞き出し、相談にアドバイスを与えた。
1日を、気持ちよく始めてもらいたい。そんな思いがあった。部下たちは、早朝電話を「目覚まし時計」と名付ける。営業マンの中に新入社員が1人いて、福島県会津地方の担当だった。山形県出身で、隣県なら溶け込みやすいかと思われたが、実は、壁にぶつかっていた。いくら酒屋を回っても、相手にされない。思い悩む日々。でも、荻田コールに救われる。いま、彼は、それを「自殺を思いとどめさせる『命の電話』のようでした」と振り返る。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント