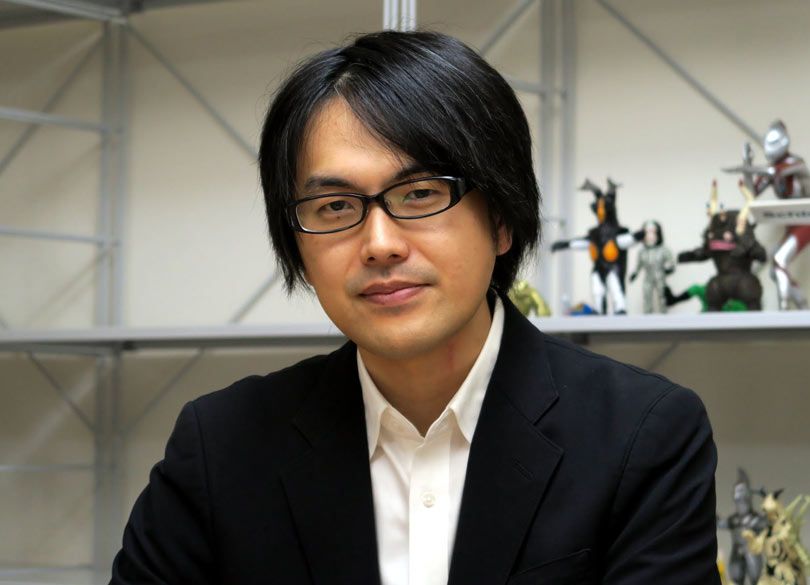何のために「一人前の国」を目指すのか
――安倍晋三首相は、かつて日本国憲法を「みっともない」と表現しました。自衛隊の明記など改憲に意欲をみせているのも、「一人前の国にしたい」という成熟へのこだわりを感じます。一方で、宇野さんは『母性のディストピア』で、宮崎駿、富野由悠季、押井守、庵野秀明という作家のアニメ作品を取り上げながら、彼らが虚構のなかで成熟を目指し、それに失敗した過程を論じました。彼らが失敗した「政治と文学」という枠組みにかえて、宇野さんは「市場とゲーム」というモデルを提示しています。どういうことでしょうか。
安倍首相や、彼に自己同一化しちゃっている人たちを見ると、日本が軍事力を行使し得る「一人前の国」になることと、自分が「一人前の大人」になることをイコールで結んでしまっているわけですよね。申し訳ないけれど、僕には彼らの「成熟」像がものすごく古く見える。
いま世界中でグローバル化へのアレルギー反応が起きています。そこで「国家と都市」という枠組みで考えてみてほしいんです。国家はバラバラなものをひとつに統合していくものですから、定義的に閉じるものだと思います。対して都市は、もともとハブ的な存在で、定義的に開かれているもの、人を自由にしていくものだと思うんですよね。
そう考えると、グローバル化というのは、実は国境が無くなるということじゃなくて、グローバル都市がどんどんネットワークを作っている、と考えられます。ニューヨークと東京とロンドンとソウルとシンガポールとサンフランシスコが、国家を無視して結びつくようになっているわけです。
国家として閉じるより、都市として開いていく
いま福岡がやっていることも、要は日本という国家が閉じるなら、自分たち都市が勝手にアジアに開きますよ、ということですよ。だから僕はグローバル化の主役は都市になるし、21世紀は国家よりも都市のほうが重要になってくると思っています。
だから今の時代、国家は多様なプレイヤーの利害調整のプラットフォームにならざるを得ない。いまの世の中で、千万単位の人口を抱えると、多様な人々の利害調整で手一杯だと思うんですよ。でも都市はそうではない。規模的にもっと自由に身動きが取れるし、それぞれの物語を語り、価値観を打ち出すことができる。国家を選ぶことのコストはものすごく高いんだけれど、都市を選ぶことのコストは低いので、都市は自由に自分たちの物語を語ることが許されているんですよね。
21世紀は家族より大きくて国家より小さな「中間のもの」としての都市や、企業のような団体が重要になっていく。そしてこの変化によって人間の成熟像も変化すると僕は思っているんです。
詳しいことは本を読んでほしいんですが、時間的な永続を担う国家から、新陳代謝が大事で、どことつながっているかが重要、つまり空間的な永続を担う都市のほうが社会像として重要になってきたとき、もっと大きな話をすると、世界と個人との関係が国民国家と市民、つまり「政治と文学」の関係から、グローバルな市場とそのプレイヤー、つまり「市場とゲーム」に置き換わったとき、僕は「父」として成熟することよりも、広い意味での「きょうだい」としてつながりをもつほうが、成熟のモデルとしていまの時代に相応しいんじゃないか、と思っているんです。「政治と文学」は家族的なコミュニティが前提ですが、「市場とゲーム」では友愛的なコミュニティの可能性を考えることができる。6部ではそんな成熟の可能性を考えています。