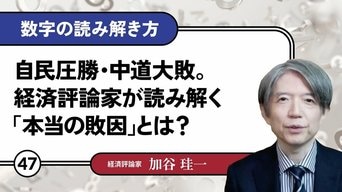この夏、日本では映画『シン・ゴジラ』が話題を集めた。「システムでは統御しがたい怪獣」を、一致団結して倒す。そのなかでも印象的だったのは「リーダーシップの不在」であった。あの結末は「それゆえ」のものなのか、「それにもかかわらず」もたらされたのか。判断は個々人にゆだねたいが、「危機のリーダーシップ」について考えされられたことは確かである。「難局」に直面したとき、われわれは指導者に何を求めるのか。いま再評価の機運がたかまっている田中角栄とチャーチルを題材に考えてみたい(後編/全2回)。
エスタブリッシュメントによるゴジラ退治
「一人の存在が歴史を大きく変え得る」実例――ジョンソンの描こうとしたチャーチル像は、「『独力型』の英雄」としてのそれである。
「往年の独力型」を引きあいに出し、現存の指導者への不満を語る。このタイプの言論を、21世紀の民衆はことさら好む。たとえば昨今の日本では、ナショナリストもリベラル左派も、こぞって田中角栄を礼賛する。
「独力型」は、既存のシステムに従属しない。同時代人にとっては、まさしく「異端児」そのものだ。このため、現役で活動する「独力型」は、しばしば激しい抵抗に遭う。チャーチルは、首相に就任する前の10年間、ずっと閣僚になれなかった。彼の奔放な言動を、周囲は警戒していたのである。田中角栄も、ロッキード事件発覚後、「政治悪の根源」として非難を浴びつづけた。
「独力型」の評価は、死後しばらくすると一転する。鬼籍に入った「往年の独力型」は、あらたに「とんでもないこと」をしでかす心配はない。彼らの「組織に縛られない行動力」だけが大衆の記憶に刻まれる。
「いま、チャーチルが(あるいは田中角栄が)いてくれたら、この停滞した状況を一気に変えてくれるのに」――そういう期待に支えられ、「往年の独力型」は偶像となる。
グローバル化が進むなか、「国家」の存立基盤そのものが脅かされている。大企業はことごとく多国籍化し、「どこかひとつの政府」の統制には服さない。富裕層はタックス・ヘイブンに財を逃がして、「いま、暮らしている土地」での納税を拒む。
「国家」は衰退し、「国民」を守る力は弱体化に向かっている。福祉や教育にあてがわれる予算も細るいっぽうだ。そういう現況を受け、少なくなった「取り分」を確保しようと、「国民」は「よそ者」を蹴落としにかかる。世界各地における「過激な排外主義の台頭」にも、そうなるだけの背景はあるわけだ。
こんな「頼りない国家」を救う術を、「あの人」ならわかっていたのではないか。多くの論者がそういう期待からいま、「往年の独力型」を語る。「国家」という「システム」そのものの危機は、「システム」を動かして事を成すタイプに克服できそうにない。「独力型」に舵とりをゆだねるべきときが来た――少なくともボリス・ジョンソンはそう考えて、『チャーチル・ファクター』を書いたにちがいない。
この夏、日本では映画『シン・ゴジラ』が話題を集めた。「システムでは統御しがたい怪
獣」を、一致団結して倒す。そのプロセスを通じて、脆弱だった「システム」が再生する。1954年公開のファースト・ゴジラは、そういう枠組みで作られていた。『シン・ゴジラ』は、それを忠実に踏襲している。
原子力は、戦後日本の発展のために導入された「危険な因子」であり、その「暴走」がゴジラを生んだ。田中角栄も、ある面においてゴジラに似ている。角栄は、経済のダークサイドに手を突っこみ、政治資金を調達する剛腕。高度成長期における「必要悪」を担っていた。そして、角栄のような「汚れ役」を総理にしないことが、戦後のエスタブリッシュメントたちの「暗黙の了解」であった。角栄は「暴走」し、その禁忌を破ったのである。