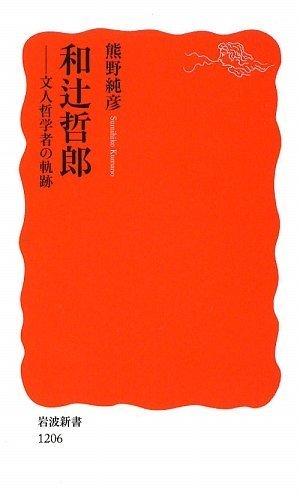熊野純彦●くまの・すみひこ 東京大学文学部教授。1958年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程を単位取得退学。北海道大学、東北大学の助教授を経て、現職。専門は倫理学、哲学史。著書に『西洋哲学史』(岩波新書)、編書に『現代哲学の名著』(中公新書)。12月には中公新書から『日本哲学の名著』を刊行予定。
東京大学駒場キャンパスの倫理学研究室において、和辻哲郎は今も「和辻さん」「和辻先生」と呼ばれているという。明治22年に兵庫県の農村に生まれ、日本で唯一ともいえる体系的哲学書『倫理学』を世に送り出した和辻は、同研究室の原型をつくり上げた哲学者だ。そして没後50年を来年に控えなお、敬称で呼ばれる存在なのである。和辻哲郎の「孫弟子か曾孫弟子」に当たる同研究室の熊野純彦教授は、「なるべく言わないようにしているんですが」と笑った。「『先生』と呼んでしまうくらいに身体化されているんですね。和辻倫理学体系に匹敵する体系的な倫理学は、いまだ日本に登場していません。この国で倫理学について考える場合、批判するにしても継承するにしても、和辻を通り抜けないままでいることはできないのです」
西田幾多郎に代表される近代日本の哲学者は、ドイツ語の訳語を一つずつつくり上げながら哲学的な思考を展開していった。そのような日本近代哲学の黎明期において、和辻は「日本語で哲学すること」にこだわった稀有な人物だったという。ゆえに彼の思考には詩的な響きが内包され、『古寺巡礼』や『風土』など、その美しい文章は当時の多くの若者を引き付けた。
「和辻の入門書として適切なのは『風土』でしょう。我々の見つめる“自然”は生の自然ではなく、人間の営みが積み重なってできている。和辻の論考は、自然と人間の関係がしばしば問題になる今という時代にも参考になるはずです」

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(二石友希=撮影)