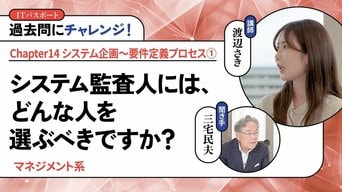2人の主人公が登場する。新卒で入社した会社を辞め、起業を志す20代の若者。そして大手不動産会社のリストラ部長を務めた後、最後は自らも会社を去ったその父親――。年の離れた親子の奮闘を通して著者の江波戸哲夫さんが描いたのは、経済不況下での様々な困難に直面しながら、それを乗り越えていく希望の物語だ。

江波戸哲夫●えばと・てつお 1946年、東京都生まれ。東京大学経済学部卒業。三井銀行(当時)を1年で退職し、出版社に勤務。83年作家として独立。著書に『ジャパン・プライド』『小説 盛田昭夫学校』(ともに講談社文庫)、『リーダーシップ原論』(プレジデント社刊)などがある。
「仕事や労働をわが手にすることは、その人の幸せに必ず繋がる。同じく仕事によって自分を表現したいという欲求は、どんな人の中にも眠っている。人生はもちろん仕事だけではないし、家族もいれば、恋人や友人もいます。それでも仕事によって社会と繋がっているという実感を持てる人は、人生の半分は幸せだと言えるのではないか、という思いが僕の中にあるんです」
本書の主人公の一人・田中雅人は、自治体の起業支援施設にオフィスを借り、アパレル系企業に提供するソフトウエアを友人と開発している。対して父親の辰夫はハローワークに通ううち、ある事件をきっかけにかつて自らがリストラした同僚たちと再会、不動産の委託販売会社を立ち上げることになる。あと少しで成功が掴めそうになったとき、雅人は狡猾な先達に足元をすくわれ、辰夫もまた悪意ある妨害を受け始める。詳細な取材に基づく2つの物語は、「仕事とは何か」という問いに答えようとするのと同時に、実際には一筋縄ではいかない「起業」の厳しさも伝えている。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(遠藤素子=撮影)