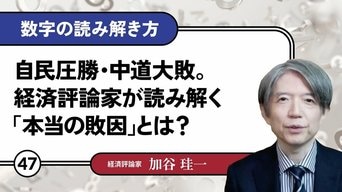なぜ認知症の患者数は増加し続けるのか
2022年から23年にかけて九州大学が発表した研究結果がある。「認知症及び軽度認知障害(MCI)の有病率調査並びに将来推計に関する研究」という長い題名のものだ。
題名は長いけれど、結論は短い。つまり、「認知症の患者は想像以上に多く、今後も増えていく一方」というものだ。高齢になると、誰もが認知症になるリスクがあるわけだ。
研究によれば2022年における認知症の高齢者数は443.2万人(有病率12.3%)、また、MCI(軽度認知障害)の高齢者数は558.5万人(有病率15.5%)と推計されている。そして、この調査から得られた性年齢階級別の認知症及びMCIの有病率が2025年以降も一定とすると、2040年には、それぞれ584.2万人(有病率14.9%)、612.8万人(有病率15.6%)になると推計される。
有病率とは65歳以上の高齢者数(3627万人、2022年)に対する認知症になった人の割合だ。高齢になると、認知症は避けて通ることのできない病気ということである。
そこで、できるだけ認知症にならずに生きていたいわたしは「酒向先生に話を聞くしかない」と判断した。それで連絡して会いに行ったのである。
「私一人ではない」チーム医療を実践する名医
まずはお世辞からである。
「酒向先生は日本一のリハビリ医ですね」
そう言ったら、ねりま健育会病院の院長、酒向正春は首を振った。
「やめてください。私はチームで診療しています。私ひとりではできません。ただ、チームは日本一だと自負しています」
わたしはとたんに謝罪した。
「わかりました。浅はかでした。すみません、それはそれとして、認知症にならないための生活の仕方を教えてください」
酒向先生は微笑する。
「最初からそう言ってください」
現在、酒向先生は練馬区大泉学園にある医療法人社団健育会 ねりま健育会病院院長を務めている。2階が病院で、3階にある老健施設もまた彼が管轄している。著書も多い人だ。NHKの「プロフェッショナル 仕事の流儀」第200回にも取り上げられている。
プロフィールは次の通りだ。
酒向先生は1961年生まれ。地元の愛媛大学医学部を卒業して脳神経外科医となった。その後、脳リハビリテーション科に転身し、医師、看護師、リハビリスタッフなどと一緒に「チームねりま」を作り、チームとして障害者や認知症の患者、家族のために働いてきた。