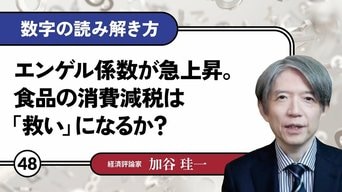フィルムの研究開発に23年間を捧げてきた技術者に、突然の異動命令が下った。彼に立ちはだかる壁。それを乗り越え、ようやく手にしたのは「手触りのある誇り」だった。

出口雄吉●電子情報機材事業本部技術・生産担当参事(写真左)。専務取締役電子情報機材事業本部長IT事業SBU長・藤川淳一氏(写真右)。京都大学理学部物理学科卒業後、23年間、フィルムの研究開発に携わってきた出口氏は「最初はPDPっていう言葉も知らなかった」という。
その日――1999年の秋――東レ・電子情報機材事業本部の出口雄吉は、三島の研修センターの一室にいた。仲間たちが見つめるその目の前では、研究をともに行う松下電器産業(現パナソニック)の技術者2人が、プラズマディスプレイパネル(以下PDP)の試作品を組み立てている。彼の開発グループではPDPの背面版技術を開発しており、2人はそれを前面版と張り合わせているのだった。
胸には一抹の不安があった。背面版には約6000本の微細な溝があり、その隔壁内で発光体が光を放つのだが、現段階ではどんなトラブルが出てもおかしくはない。半導体が1つでもショートすれば画面は美しく映らないし、隔壁に小さな埃が付着している可能性もある。
このプレゼンは東レの「技術開発総合報告会」の一環として開かれたもので、社長をはじめとした重役たちがPDPの成果を見に来ることになっていた。ここでの印象の良し悪しは、研究の今後にも大きな影響を与えるだろう。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント