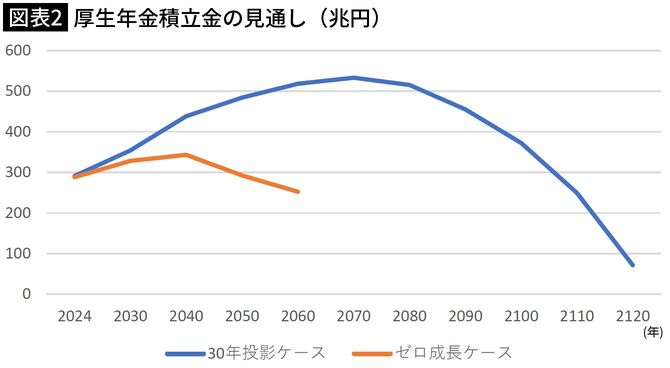給付の切り下げは粛々と実施される
今回の財政検証では、厚生年金のモデル世帯(会社員の夫と専業主婦)で、所得代替率(現役世代の平均手取り賃金との比率)が、2024年の61.2%から2057年の50.4%に低下する(「標準」ケース、以下同様)ことが示された。このモデル世帯の「所得代替率が5割維持」により、厚労省は年金制度の安定性が保証される、としている。
国民は節穴ではない。そんな理屈が通用すると思っているのだろうか。
OECD(経済発展協力機構)による国際標準の所得代替率は個人単位であり、日本における個人単位の所得代替率(税引き後)は2023年で39%と、すでに5割以下だ。
2024年の61.2%から2057年の50.4%に低下(5割維持)するという前出の厚労省の「日本型所得代替率」は、保険料負担なしに基礎年金を受給できる専業主婦という、今後、減少する一方の、特殊な世帯について水増しされた指標に過ぎない。いわば、見え見えのトリックである。今後も、そうした過去の世帯類型を基準とした年金制度でよいのだろうか。
被用者が支給される厚生年金などは、モデル世帯・月額ベースで2024年の月額23万円から、2057年には約4万円減っている。年間にして約49万円の大幅減だ。
2019年、金融庁は65歳世帯の老後30年間の生活を支えるには2000万円の貯蓄が必要という報告書を発表した。だが、現にもらう年金額が減るということは、さらに不足する額が増えるということであり、一橋大学名誉教授の野口悠紀雄氏の指摘によれば3500万円以上に上方修正が必要だ。
報酬比例部分(いわゆる2階立て部分)のない基礎(国民)年金のみの単身高齢者については、さらに悲惨だ。2024年の月額6万5000円の基礎年金も2057年には2割減の5万2000円となる。
なお、この減額を少しでも小さくするために導入しようとしたのが、国民年金の保険料納付期間を現行の40年間から45年に延長することで、基礎年金受給者の所得代替率を50.4%から57.3%に引上げる仕組みであった。
これは給付額の半分を国から補助される国民年金受給者には有利な仕組みだが、国会で野党から実質増税であるとの批判があると、早々に撤回された。年金財政のためには望ましい改革案だったと思われるが、与党による目先の選挙対策で潰された形となった。
世帯類型の違いによる年金の負担と給付も示されたが、世帯所得が同じ「専業主婦世帯」と「共働き世帯」を比較して、両者の差はないという結論は恣意的である。あくまで「世帯主」の所得を同一水準に固定した上で、同じ保険料負担なら同じ給付というのが保険の大原則だ。
単身者にはないのに、なぜ専業主婦を持つことで、追加的な保険料負担なしに基礎年金が余分に受け取れるのか。実は、昔は違った。1961年改正以前には、厚生年金の被保険者の大部分が、配偶者の家事負担の労に報いるために、独自に国民年金保険料も追加負担していた歴史を隠してはならない。
世代間の格差について、年金額が毎年削減される現行制度では、モデル世帯の所得代替率が現65歳の61.2%と比べて30歳では50.2%と、初期時点の給付額がすでに18%も少ないことも示された。