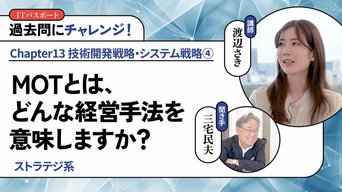トイレの流し方の不思議
みなさんはトイレの水を流す時に、節水を意識していますか?
最近のトイレの流し方は、多様化しています。例えば、レバーを押すタイプ・レバーでひねるタイプ・ボタンを押すタイプ・センサーに手をかざすタイプなど……。いろんなタイプがあり、「流し方が分からなかった」「流す部分が見つけにくくて戸惑った」なんて経験があるのではないでしょうか。
その上、流す部分をよく見てみると「大」や「小」と選べるようになっており、「eco小」なんて表示があるケースがあります。これは一体どんな違いがあるのでしょうか? どうやって使い分けたら良いのでしょうか?
「大」と「小」の違いとは
例えば「大」と書いてあれば、大便(ウンチ)を流す時に使用すれば良いと思うでしょう。同様に「小」と書いてある場合は「小便(おしっこ)」を流す場合に使用すればいいと想像できます。これは正しい判断です。しかしせっかくなので、「どんな違いがあるのか」を理解すると、さらに良い使い分けができるかもしれません。
まず、洗浄水の条件の基準を定めているJIS(※)の掲載文を要約すると、「大洗浄」の条件は、「JIS P 4501に規定するトイレットペーパー(1枚重ね)を、長さ約760mmに切り、直径が約50mm〜75mmの球状に緩く丸めたもの7個を、トラップを満水にした後、一度に便器内に投入し、直ちに大洗浄を行い、完全に便器外へ排出されること」と書いてあります。「小洗浄」の場合には、同様に球状の物が3つ流れるか? が基準となっています。
つまり大の洗浄の場合は、76cm×7個=532cmのトイレットペーパーが無事に流れれば良く、小の洗浄の場合には76cm×3個=228cmのトイレットペーパーが流れるのが、正常だといえます。なお、トイレットペーパー以外に、疑似汚物と呼ばれる特殊な素材で作った「ウンチの代用物」を流して性能を試すなど、メーカーごとに検査方法や基準は異なることがあります。
なお、先ほど紹介した「JIS P 4501に規定するトイレットペーパー」は、水で崩れやすいのですが、最近は温水洗浄便座用の厚手のふんわりしたトイレットペーパーが流通しています。これらは溶けるのに時間がかかるので、洗浄水を多めにしたほうが良いでしょう。
(※)参考文献:JIS A 5207:2019 衛生器具―便器・洗面器類
P.9の「8.2.1.2 排出性能試験」でのb)-3)及びd)-3)では小洗浄について述べられています。要約すると、ペーパーを丸めたものを3つが排出されることが小洗浄の基準になっています。