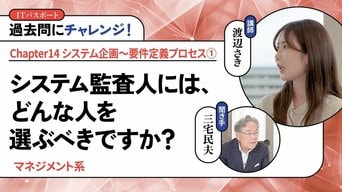関空での新発想「週末グアム」

全日本空輸社長 伊東信一郎●いとう・しんいちろう
1950年、宮崎県生まれ。74年九州大学経済学部卒業、全日本空輸(ANA)入社。99年社長室事業計画部長、2001年人事部長、03年取締役営業推進本部副本部長兼マーケティング室長、04年常務、06年専務、07年副社長。09年4月より現職。
1950年、宮崎県生まれ。74年九州大学経済学部卒業、全日本空輸(ANA)入社。99年社長室事業計画部長、2001年人事部長、03年取締役営業推進本部副本部長兼マーケティング室長、04年常務、06年専務、07年副社長。09年4月より現職。
94年9月4日、関西国際空港が開港した。当時43歳。国内外で発着枠を獲り、どの飛行機をいつ、どこへ飛ばすかというダイヤグラム(運行表)を編成する「ダイヤ屋」と呼ぶ部門の課長職にいた。
関空は「24時間離着陸が可能」をうたい文句に、内外の航空会社の新路線を呼び込んだ。でも、国内では、ほかに夜遅く離着陸を認めている空港は、ほとんどない。だから、夜に着陸すると、翌朝まで駐機させておくことが多い。ときには、ジャンボ機がひと晩、遊んでしまうこともある。大きなロスだった。
そこで、考えた。「片道3時間余りのグアムへ飛ばせば、翌朝までに往復できないか?」。調べると、運行表上は可能と出た。569席あるジャンボ機を夜間も飛ばせれば、かなりの収入になる。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント