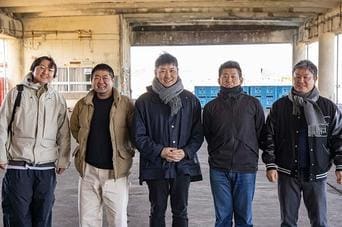新作は年10冊ペース、9年連続で長者番付に
今話題のKADOKAWAにとって、数十年に1人の“ドル箱”だった経済小説の巨人がいた。自宅のリビングには、出版累計部数の大台突破記念に贈られた女神や天使のブロンズ像、銀製の船の置物などがずらりと並ぶ。角川書店(現・KADOKAWA)の角川歴彦社長(当時)から直接手渡された、角川文庫1000万部突破記念(平成5年)と、同作品数100点突破記念(同7年)の記念品もある。
作家の名は、清水一行(1931年-2010年)――。生涯に出した作品数は214で、城山三郎の118作品の倍近く。本の販売部数は5000万部超という怪物である。
清水氏が『小説兜町』をひっさげ、三一書房から文壇に華々しく登場したのは昭和41年(1966年)、35歳のときだった。日興証券を日本一に押し上げた同社第1営業部長の斎藤博司氏をモデルにした作品で、証券業界独特の符牒をふんだんに使って相場の熱気を再現し、単行本だけで約20万部を売り上げた。それ以降、年に8~12冊という驚異的なペースで新作を発表し、9年連続で長者番付入りした。
清水氏の作品群は、ありとあらゆる業界の表裏を描き、そのまま昭和から平成にかけての日本経済史になっている。
大企業の暗部から重役同士の権力闘争まで
例えば、総会屋の芳賀龍臥がやっていた、企業を徹底して食い荒らすアウトローの貸金業を描いた『虚業集団』、トヨタ自動車販売会長の神谷正太郎をモデルにした『一億円の死角』、松下電器をモデルに、小売価格を強制して市場を支配しようともくろむ電器メーカーと、反発する小売店のつばぜり合いを描いた『怒りの回路』、新幹線公害をテーマに、日本推理作家協会賞を受賞した『動脈列島』、日産自動車の「天皇」と呼ばれた労組トップの塩路一郎をモデルにした『偶像本部』などは、高度経済成長期を牽引した大企業の波乱の内幕を描いている。
企業の重役にスポットを当てた小説も話題を呼んだ。京都産業大学をモデルに大学経営の実態をえぐった『虚構大学』、高島屋の女性重役、石原一子をモデルにした『女重役』、政商・小佐野賢治を実名で描いた『花の嵐』、本田技研工業の藤沢武夫副社長について世評とは違う視点を提供した『器に非ず』、ゼネコンの裏金対策部長の苦悩を描いた『裏金』、大阪商工会議所の会頭争いを描いた『小説財界』、大手洋酒メーカーの同族経営の実態を描いた『影法師』、全日空経営陣3人の権力闘争を描いた『三人の賢者』など、作品群のごく一部を紹介しただけでも、扱うテーマの広さがよく分かる。