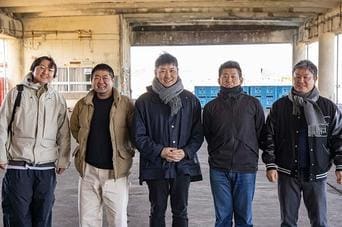※本稿は、平松類『新版 老人の取扱説明書』(SB新書)の一部を再編集したものです。
家庭内で起きる高齢者事故の半分は「転ぶ」
高齢者の事故の中で最も多いのは、外ではなく家の中です。独立行政法人国民生活センターの報告によると高齢者の事故のうち77.1%が家庭内で起こっています。さらに、65歳以上は大きな事故の割合が2倍になります。なぜなら、筋肉・骨が弱くなるからです。
家庭内で起きる事故で多いトップ2は、転落(30.4%)、転倒(22.1%)。つまり半分以上は、転ぶという事故なのです。特に階段で転んでしまうと危険で、最も骨折が多いのは階段での転倒です。
足の骨折というと松葉杖をついて生活するのを想像するかもしれませんが、若い人の骨折と違い、高齢者の骨折はもっと深刻です。要介護4、5という多くの介護を必要とする状態の原因は、認知症・脳卒中の次が骨折です。
足の骨折は、若い人ですと足の長い骨の骨折が多いのですが、高齢者の場合は大腿骨頸部骨折という足の付け根の骨折が多くなります。高齢者がこうなってしまうのは、骨が弱くてスカスカになる骨粗鬆症になりがちだからです。しかも大腿骨頸部骨折は、松葉杖で歩くことも困難になり、人工関節の手術が必要で、寝たきりのきっかけとなる代表的な骨折でもあります。
高齢者が家の中で転ぶというのは、寝たきりにもつながる一大事と心得て、転倒防止につとめるのが大事なのです。
年を取るほどバランス能力は衰えていく
高齢者が階段などで転びやすい原因は何でしょうか? それは、「重心(バランス)」と「目」が大きく関係します。
高齢になると、重心は不安定になります。20・30代と比較すると60代で20%バランスを失い、70代では41%、80代以降では80%バランス能力を失います。
しかも高齢者は若い人と違い、軽く前傾するだけで重心が不安定になります。さらに高齢者は階段の上り下りでは前傾しがち、つまり重心をくずしがちとなり、よく転ぶのです。前傾がダメだからといって反り返ったとしても、今度は滑って転びやすくなってしまいます。前傾も反るのも危険なのです。年を取ると難しいかもしれませんが、階段でもどこでも重心を安定させて歩く癖を身につけるのが大事となります。