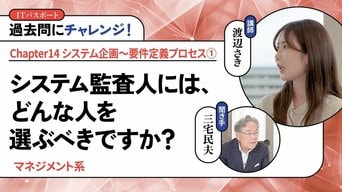人は誰でも愛読書が一冊はあるものだが、科学者も同じである。本書は自然科学と何らかのつながりを持つ64人が、宝物のような「私の一冊」を語ったものだ。副題に「『鉄腕アトム』から『ユークリッド原論』まで 」とあるように、取り上げられた書籍はマンガ本からフランス語の学術書までさまざまである。月刊誌「科学」(岩波書店)に5年ほど連載された「心にのこる一冊」がもとになっている。
科学者は自分の感性を極力出さないように振る舞うが、プライベートな読書の世界を開示してみると意外な姿が現れた。知への強い情熱を持つだけではなく、体には熱き血潮が流れ、また哀しみに心痛める生身の人間が透けて見えるのだ。
本書は、1 夢(すべてのはじまりはここに)、2 学ぶ(この一冊に育てられ)、3 転機(出会ってしまったばかりに)、4 縁(めぐりあわせの妙)、5 衝撃(目眩がするほどに)、6 敬慕(先達をあおぎみる)、7 礎(いくつになっても読み返す)、という非常にオシャレな題の付いた7つの章からなる。中身を見ていこう。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント