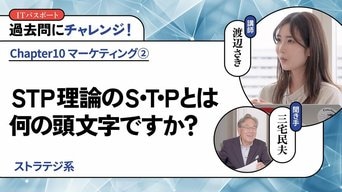世界第2位、カザフのウラン争奪戦

図を拡大
新興国を中心に活発化する「原子力」案件の動き
新興国を中心に活発化する「原子力」案件の動き
これらの動きを一番喜んだのは、日本の原子炉メーカーだ。彼らは90年以降、逆境に阻まれながらも、コンスタントに原子力発電所を建設し続けてきた。そして“原子力ルネッサンス”の機運を一気に高め、原子力大国への可能性を具体的に示したのが東芝だった。
世界14カ国に34カ所の拠点を持ち、100年を優に超える歴史を持つウエスティング・ハウス(WH)は原子力業界の巨人。そのWHを東芝が6000億円(当時)を超える巨費を投じて買収した。
西田厚聰社長(当時)が、「(WHの)買収によって、当社は今まで見たこともない世界に乗り出した」と振り返るほど、東芝によるWH買収は衝撃的だった。事実、この直後、中国から四基の原発を受注した東芝だが、同買収についての中国の報道はまるで米国企業が受注したようなトーンだった。まさにWHは米国の象徴で、原子力の世界では米国企業そのものだったからだ。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント