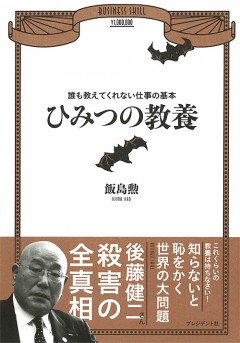なぜ、弁護士は頼りにならないか
飲食店の産地偽装が大きな問題になったときが、かつてあった。私はある外資系ホテルから、こんな相談を秘密裏に受けたことがある。
「レストランのメニューに書いてある牛肉の産地が実際のものと違い取り調べを受けている。公正取引委員会出身の弁護士に当局との交渉を依頼したのだが、ラチがあかない。このままでは営業停止になり、社会的にも糾弾されるかもしれない」

「この問題の争点は、産地偽装の有無ではなく、産地偽装が故意か否かである。故意でなければ始末書だけで済むのでレストランは痛手を受けない。その弁護士が捜査当局とどのようなやり取りをしているか知るすべがないが、あなたがやるべきことは明白だ。当局に対して『本来であれば、違う産地の牛肉を使用した時点で、リアルタイムでメニューの書き換えをすべきだったが、たまたまその牛肉が手に入らなかったときに、厨房とフロアの意思疎通がうまくいかなかった。客をごまかそうという意図はなかった』というストーリーに従って想定問答集をつくり、従業員で見解を統一しなさい」
私があとでその弁護士の素性を調べると、公取出身という経歴は正しいのだが組織の中でずいぶんと評判が悪くて、弁護士として独立していたことがわかった。さらには想定問答集をつくってもいなかったことが判明した。想定問答集をつくっていないということは、当局に白旗を上げていることと一緒だ。闇雲に「ごめんなさい。助けてください」というのでは、助けられるものも助けられなくなる。どこは認め、どこで戦うべきか。それが大事なのだ。