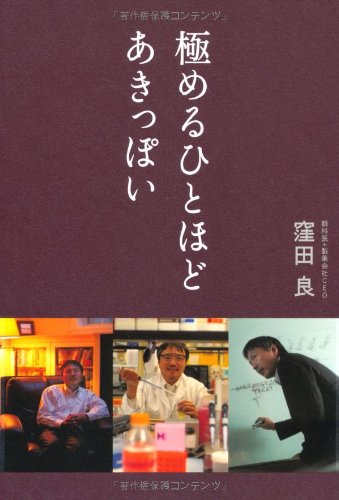世界で1億2000万人が患う「加齢黄斑変性」
白内障や緑内障などと同じように世界では患者数の多い疾患でありながら、日本では加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい)はまだあまり知られていないようです。最近では再生医療分野で加齢黄斑変性のウェット型がiPS細胞の実用化ターゲット疾患に指定されていることもあって、ニュースで見聞きされたかたもいらっしゃるかもしれません。失明の恐れがある目の病気であるにもかかわらず、現段階では一部の末期患者さんしか治療対象ではないので、より多くの患者さんに使える新しい治療薬の開発が望まれている病気です。
加齢黄斑変性は、加齢にともなって網膜の視力をつかさどる黄斑部が変性し、症状 が進行するにつれて中心視力の低下をひきおこす病気です。深刻なケースでは失明に至ることもあり、欧米では失明の主要原因と言われています。加齢黄斑変性は大きくわけて「ドライ型」と「ウェット型」があります。初期のドライ型からそのまま末期に進行するか、途中でウェット型に転換します。割合で言うと、初期のものも含めたドライ型が90%、末期のウェット型が10%を占めています。

ところで加齢黄斑変性はどういうものなのか。この病気は、最初に「ドライ型」から発症します。初期段階では網膜に老廃物が溜まるのですが、自覚症状は現れないか、現れたとしても乏しいです。さらに進行すると視細胞がポツポツと抜け落ちるように損傷していきます。(視細胞はデジタルカメラのCCDに例えるところの画素にあたります。)それがやがては点から面になり、見えないところが視野の中心部から地図状に広がっていっていきます。これが末期の地図状萎縮を伴うドライ型加齢黄斑変性です。
一方、ドライ型のまま末期に進行するのではなく、途中でウェット型を発症するケースがあります。正常な状態では存在しない新しい血管が網膜組織につくられて黄斑部に凹凸をもたらすため、視力の低下や視野の歪みが生じてしまいます。それが進行すると新しい血管はもろくて破れやすいため、出血を伴うこともあります。まるでCCDの前に赤い絵の具をこぼしたかのような状態になります。必ずしも画素が無くなっていないにせよ、視力は障害されます。
加齢黄斑変性では見えなくなるところが、視野の中心部なので、字を書いたり、コップにお茶を注いだりする日常的な動作が困難になってしまうのです。