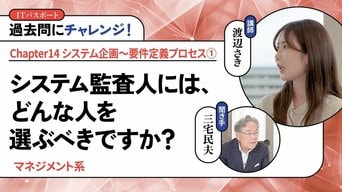勝負強い監督、接戦に弱い監督……、監督の発想は、すべて現役時代のポジションから湧き出ている。歴代監督をポジション別に徹底分析する。
「江夏の21球」を生んだ監督の采配
1979年11月4日、大阪球場。広島対近鉄の日本シリーズ第7戦は、『江夏の21球』(山際淳司著)として、あまりにも有名だが、肝心な部分が欠落している。“知将”古葉竹識(広島)と“闘将”西本幸雄(近鉄)の心情がまったくといっていいほど描かれていない点だ。しかし、古葉に取材すると、二遊間出身(二塁手として632試合、遊撃手として796試合に出場)の監督らしく、随所に緻密な采配を揮っていた。
まずは、広島が4対3と1点リードして迎えた9回裏、近鉄の先頭打者、6番・羽田耕一(三塁手)がセンター前ヒットで出塁。代走・藤瀬史朗が二盗を試み、水沼四郎捕手が悪送球し、無死三塁になった場面である。
「田中(尊)ヘッドコーチをマウンドに行かせました。ボールがつづき、フォアボールになっても構わんと投手の江夏(豊)に伝えたんです。そのあと走られて、二、三塁になったら、それはそれで仕方がない。満塁で勝負しようじゃないか、とそこまでいいました」
実際、7番クリス・アーノルド(二塁手)が四球を選ぶと、西本は俊足の吹石徳一(女優・吹石一恵の父親)を代走に送った。
そのとき、江夏は意外な光景を目にし、にわかに落ち着きを失う。三塁側ブルペンへ池谷公二郎と北別府学の両投手が走っていったからである。
(わしがそんなに信用できんのか)
江夏のプライドが傷ついたのだった。
だが、監督の古葉は冷静であった。
「日本シリーズの引き分けは4時間半。まだ1時間以上あった。同点になったら、攻撃して点を取らなくてはならない。当然、江夏に代打を使うケースも出てくる。そういうとき、次の投手を用意していなかったら、指揮官失格ですよ。ただ、9回裏の場面で江夏を代えようという気持ちは皆無だった」
指揮官は最悪のケースを含め、ありとあらゆる場面を想定し、準備しなければならない。古葉の深謀遠慮は、監督として当然だろう。
彼に取材した場所は、東京・千代田区にあるフランス料理店の個室。濃紺の背広に同色のネクタイ。髪をきれいに7・3に分けた古葉は、巧みにナイフとフォークを使い、野球の采配同様、一分のすきもなかった。
8番・平野光泰(中堅手)の3球目、一塁走者の吹石がスタート。捕手の水沼は三塁ランナー藤瀬の本塁突入を警戒し、二塁へ送球せず、吹石は楽々と二塁を陥れた。無死二、三塁。こうなれば、広島は満塁策しかない。古葉は平野の敬遠をバッテリーに指示した。