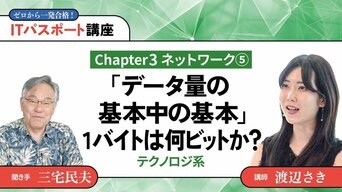政府は、中長期のエネルギー政策の指針とする「エネルギー基本計画」を、4月11日の閣議で決定した。民主党政権が掲げた「原発ゼロ」を白紙撤回し、原子力発電を安定した電力を供給できる「重要なベースロード電源」と位置付け、国内48基がすべて停止中の原発の再稼働にゴーサインを出した。しかし、再稼働を急ぎたい電力各社はそれとは裏腹に、再稼働に巨額資金を要する老朽炉について、廃炉の検討も同時に視野に入れ出した。法律で定める原則40年の運転期限に近づく30年超の老朽炉は16基と3分の1を占めており、老朽炉問題は、政府が基本計画で総発電量に占める原発の構成比の目標値を見送らざるをえなかった「不都合な真実」にも映る。
老朽炉廃炉の口火を切ったのは、3月29日に運転40年を迎えた島根原発一号機(松江市)を抱える中国電力だった。苅田知英社長は「(島根一号機は)廃炉にする選択肢もある」と、廃炉に含みを持たせた。これに続き、四国電力の千葉昭社長も、運転36年の伊方原発一号機(愛媛県)について「あらゆる可能性を捨てずに検討」と言及した。その背景には、老朽炉を稼働するとなると巨額の資金投入が避けられぬ厳しい現実がある。
運転期限40年を超えても稼働延長は必ずしも不可能でない。ただ、それには原子力規制委員会の安全審査をはるかに上回るハードルを越えなければならず、巨額投資は避けられない。原発停止で業績不振に喘ぐ電力各社にとって、老朽炉は「動かしたくても動かせない」大きなお荷物となり、勢い再稼働よりは廃炉がプラスとの判断に大きく傾きつつある。
仮に巨額投資に踏み切ったとしても、電力システム改革により電力小売りの完全自由化、発送電分離が実現した段階で、原発は投資額を含めて最も高いコストの電源になる可能性は否定できず、電力各社が老朽炉の再稼働に二の足を踏まざるをえない大きな要因になってきた。こんな事情を背景に、原子力産業界にも「既存原発は今後、再稼働か廃炉かで選別されるのは必至」との見方が強まっている。
「3.11」前に30%あった原発の電力構成比は、新増設がなければ15%程度に半減するとの悲観論も浮上し、否応なしの「縮原発」を迫られそうだ。