「作家のメタファー」としての長距離選手
ところで、春樹がマラソンやトライアスロンに長年、挑戦していることは有名です。マラソン・ランナーについても、印象ぶかい文章をいくつか残しています。
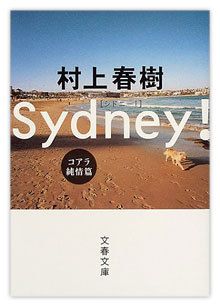
[著]村上春樹(文藝春秋)
「素顔の犬伏は職業的マラソン・ランナーには見えない。いわゆる「体育会系」という雰囲気でもない。何に見えるかというと、クールで個人的な、独立心の強い、特殊技術の専門家のように見える。その技術はあまりにも特殊な種類のものなので、一般の人にいちいち説明する気が起きないのだと言いたげな感じだ。説明できないことなんだから、わかってもらえなくても仕方ないと心の底で思っている。そういう印象がある。傲慢というのではない。ただ相手との間に、あくまでリアリスティックに、適度の距離を置いているだけだ。」(『Sydney!(1)コアラ純情篇』)
シドニーオリンピックの男子マラソン代表だった、犬伏孝行の描写です。この文章は、
「マラソンを愛好する小説家が、トップランナーを好奇のまなざしで見ている」
というのと、あきらかにおもむきがちがいます。いくら春樹が「大作家」だからとはいえ、実在する他者の内面について、ここまで「知ったふう」なことを書いていいのか――読みながら、そんな疑念さえわいてくる叙述です。
私の想像では、「総合力勝負の小説家」という、前例のない存在を構想するうえで、春樹はマラソン・ランナーからイメージを借りています(上の引用文のなかの「特殊技能の専門家」とは、じつは「小説家」のことではないでしょうか)。春樹は犬伏に託して、じぶんを語っているのです。
引用したくだりのすこし前、長距離ランナーのフォームに言及した部分に「彼らは普通でないサーキットに入ってしまった人々なのだ。」という一節が見られます。べつの著作のなかで、
「小説を書くというのは、一種の非現実的な行為なので、ある時期きっぱりと日常を離れることがどうしても必要になる」(『意味がなければスイングはない』)
とのべていますから、マラソン・ランナーと小説家のあいだに共通するものを、春樹がみとめていたことはあきらかです。
そんな春樹が、『走ることについて語るときに僕の語ること』を書いたのは当然といえます(春樹はこの本を「走ることを通した自叙伝」と呼んでいます)。しかし、『走ること~』は、犬伏について書かれた文章のようには、私の心にせまってきません。
他人に託してじぶんを語る場合、ふだんなら口にできないような心の深いところまで、衒わずにのべることが可能です。「他者」というフィルターをもうけたほうが、かえって「偽らない本音」をいえるのです。犬伏という「長距離ランナーの孤独」をとおして、春樹はじぶんという「小説家の孤独」を語り、読む者の心を揺さぶります。
これに対し、『走ること~』のなかでの春樹は、身がまえているように感じられます。マラソンという競技への敬意がつよすぎて、「じぶんのようなアマチュアランナーが、こんなことを書いて大丈夫だろうか?」 と疑っているようすが見えるのです。そのせいか、この書物を公表する意義や、「走ること」についてどれほど真剣であるかについて、肩ひじを張って説明しています。

