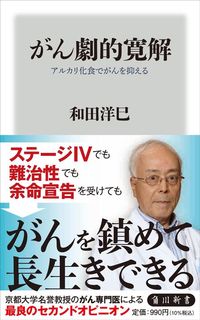患者が副作用で苦しんでいても譲らず…
抗がん剤は、毒性に関する臨床試験、用量に関する臨床試験、効果に関する臨床試験などを経て、使用可能な治療薬として正式承認されます。このうち、用量に関する臨床試験では、副作用がギリギリ許容できる用量で、かつ、薬剤の効果を最大限に引き出せる用量が決められます。
そして、決定を見た用量はレジメンに「極量」として記載されますが、副作用がギリギリ許容できる用量は「安全な用量」を意味しているわけではありません。極量は「効果を最大限に引き出すためには、すなわちがん細胞を殲滅するためには、一定程度の副作用死はやむを得ない」とする考え方から導き出された用量なのです。
したがって、耐えがたい副作用に苦しむ患者が抗がん剤の減量を訴えても、ほぼ例外なく、がん治療医は「極量で治療しなければ、抗がん剤は効かない」と言って譲りません。患者や家族らが抗がん剤治療の中止を訴え出た場合には、「当院では応じられないので他院へ」などと言われ、冷たく突き放されてしまうことさえあります。
私は、標準がん治療をすべて否定するつもりはありません。しかし、少なくとも治らないとされているIV期がんに対しては、がんを殲滅するという古い思想から脱却してその限界を補う治療体系が必要だと考えています。完治が無理でも、患者さんが日常生活を取り戻せるような新たな治療体系を構築することが切に求められているのです。
がん治療は100年以上も変わっていない
近年は抗がん剤以外にも分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬などが延命を主な目的として使われるようになりました。しかし、新たに登場したこれらの薬剤もまた「がん細胞を殲滅する」という思想に縛られたまま使用されています。
分子標的薬は単独で使用される場合も、あるいは抗がん剤と併用して使用される場合もありますが、その使用量は先に述べた最大使用量(極量)を求める方法で決められます。そのため患者は強い副作用にしばしば苦しめられますが、がん治療医はなかなか薬剤の減量を考えてはくれません。また、免疫チェックポイント阻害薬は抗がん剤治療で効果が認められなかった患者に投与することが前提となっているのです。
殲滅思想という点では、手術や放射線治療も事情は同じです。手術は言わばがん病巣を物理的に根こそぎ取り除く治療であり、放射線治療もがん病巣を放射線で叩きのめす治療だからです。ただし、前述したように、III期までの固形がんの場合、手術や放射線治療で治癒が期待できる点が抗がん剤治療とは事情を異にしています。
ちなみに、オーストリアの外科医、テオドール・ビルロートが世界で初めて胃がんの手術に成功したのは1881年のことです。近年はロボットを使った腹腔鏡手術をはじめとして新たな術式が開発されていますが、がん病巣を物理的に根こそぎ取り除いて殲滅するという本質に違いはありません。
結局、がん治療をめぐる思想は、実に100年以上、何も変わっていないのです。