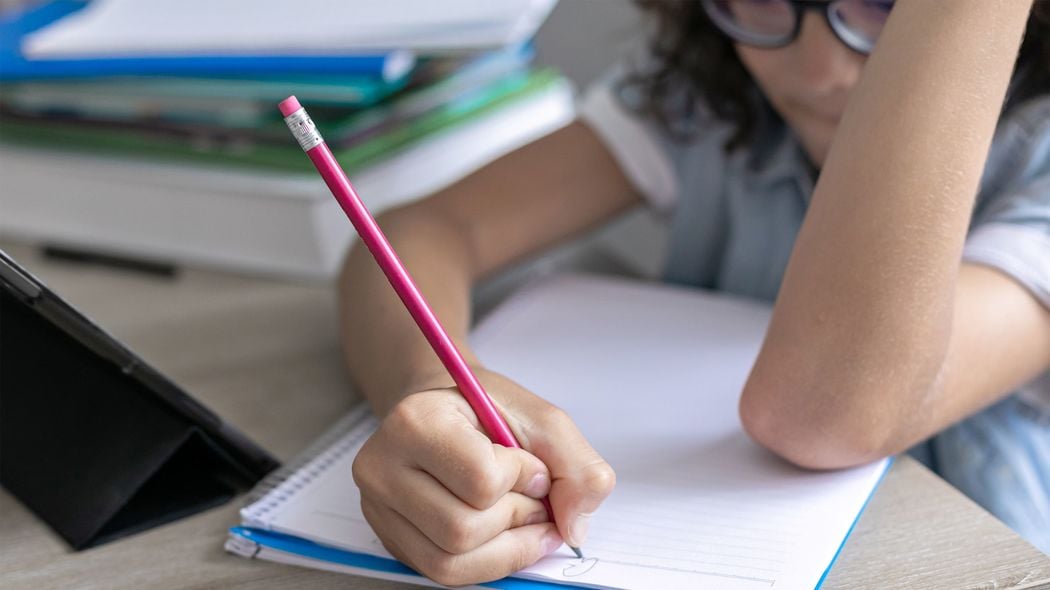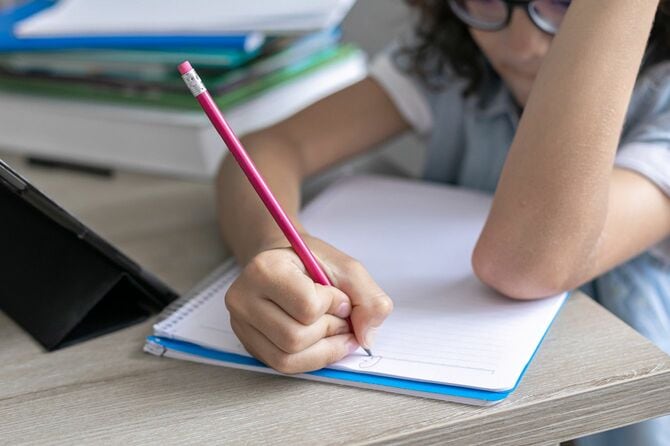子供部屋を片づけたら成績が伸びた!
いざ勉強しようと思っても、どこに何があるのかわからない。必要なものが見つからないから、やる気にならない……。子供が勉強しない理由の一つに、部屋が散らかっているということがあるようです。大抵は、勉強机にしても必要ないものがたくさん積みあがり、ぐちゃぐちゃになっているんですよね。
例えば、過去に相談を受けた小学生2人のお母さん。中学受験に向けて塾通いしていたけど、全く成績が伸びず、塾を辞める辞めないで親子喧嘩が絶えなかったらしいのですが、勉強机の周りを片付けたところ、偏差値が30台から60台にあがってびっくり。塾の先生から電話がかかってきたそうです。その後、無事に志望校に合格されました。
そのほかにも、子供部屋を片づけたあと「自分から勉強するようになった!」「成績が伸びた!」「行きたい学校に合格した!」、そんな話をたくさん聞きます。
なぜ部屋を片づけたら、勉強するようになるのでしょうか? それは子供が“自己管理”できるようになるからです。
自己管理とは、自分の感情や行動をコントロールして、目標を達成すること。
時間管理や健康管理もそうですが、片づけも自己管理の基本中の基本です。自己管理能力が高まれば、子供の成績アップにつながります。
私は、現在東大現役合格率の高さで話題の神奈川の超進学男子校・聖光学院の生徒さんへ向けて「時間術」「整理術」に関するセミナーを開催していますが、これは保護者と学校の先生から「ぜひ生徒向けに、片付けのセミナーを」と言っていただいたのが始まり。生徒からの申し込みが100名を超えるなど、いかに「自己管理」が重要か、興味・関心の高さが伺えます。
片づけの前の……2ステップ
では具体的に、子供部屋は、どのように片づけていけばよいのでしょうか。片づける前に、以下の2つのステップをふまえることが大切です。このステップを踏むことで片付けを「自分ゴト化」させます。
ステップ1:「メリット」「デメリット」を書き出す
まずは子供自身に、片付いた理想の部屋をイメージしてもらいます。そのうえで、「片付いた部屋のメリット」「散らかった部屋のデメリット」それぞれを考えてもらい、紙に書き出してもらうのです。
まずは、片付いてすっきりした部屋、そこで過ごす自分を浮かべたあとに、どんなメリットがありそうか聞いてみましょう。「必要なものがすぐに取り出せる」「集中して勉強ができる」「次の日の準備が早くなる」、そうなると「忘れ物がなくなるから、学校でも快適な学習環境が整う」などが出てくるでしょう。
一方、散らかった部屋(今)のデメリットも聞きましょう。「必要なものが見つからない」「お母さんに怒られる」「自分も気分が悪くなる」「やる気が削がれる」「学校の準備がうまく整わない」、そうなると「忘れ物が増えて、先生や友だちに迷惑をかける」、「学校に行くのがいやになる」などが出てくるかもしれません。
そんなふうに、片付いた部屋と散らかった部屋で過ごす自分を比較することで、4月から「どちらがいいか」を考えさせ、子供自身が「片づけたい!」と思うようにマインドをセットします。
ステップ2:必要なものだけ残す
次に、必要なものと不要なものを分けていきます。
例を挙げると、これまで使用した教科書やテスト用紙は、次の学年で必要そうであれば残すけれど、それ以外のものは処分します。すべてとってある家庭もありますが、そうすると何がいちばん必要かわからなくなるので、取捨選択が必要です。
また勉強関連のものだけでなく、習い事の道具やゲーム、おもちゃも「要」「不要」に分けて、不要なものは処分しましょう。