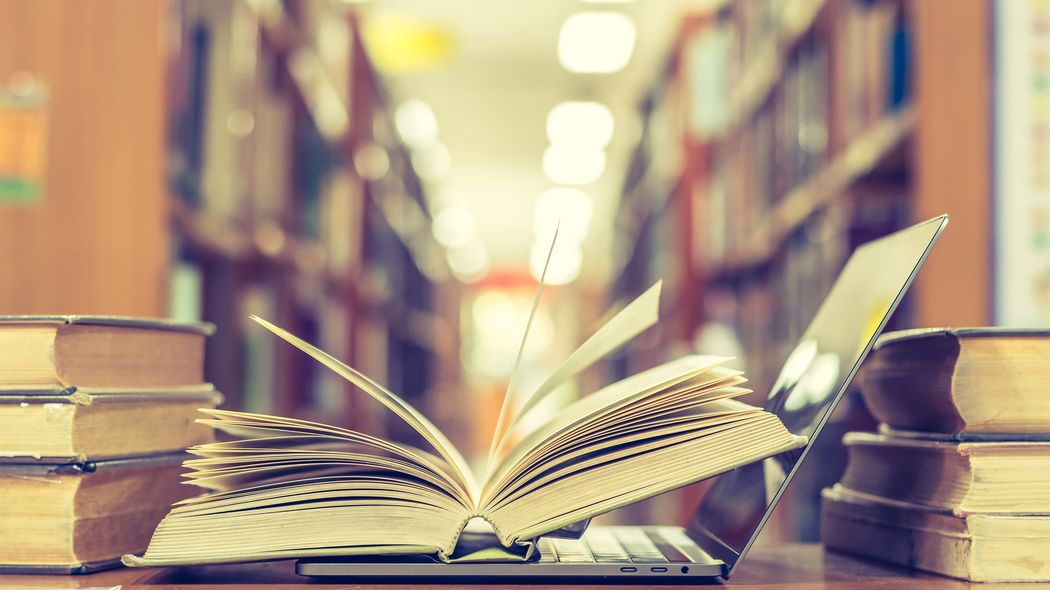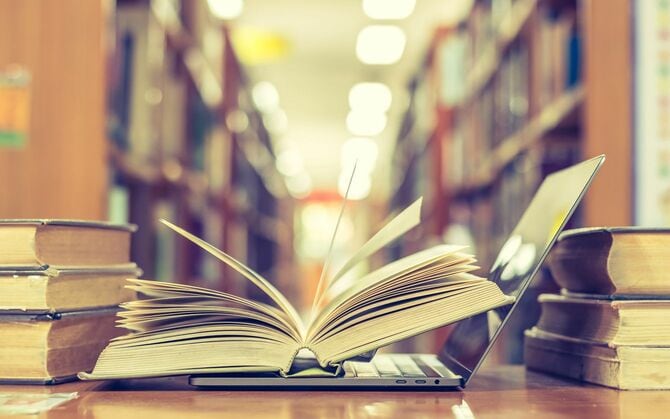※本稿は、竹中亨『大学改革 自律するドイツ、つまずく日本』(中公新書)の一部を再編集したものです。
ドイツの大学における内部任用の禁止
人事のあり方も自己規律との関連で興味深い。大学にとって人材の質は生命である。いくら研究設備が最新鋭であっても、優秀な研究者がいなければ宝のもち腐れである。だから、どの大学も優れた研究者を教授に獲得すべく、人事には最大の努力をはらう。
大学の人事は外部からは見えにくい面がある。人選の条件はポストごとに異なるし、さらに教育・研究の内容は専門的だから、最善の人材が教授に選ばれたのかどうかは外からは判断しにくい。そこで、外部の目が届きにくいのをよいことに、仲間うちの馴れあいに流れる危険が生じる。馴れあいを排し、質を最優先した人事選考をいかにして可能にするか。そこでも鍵になるのは自己規律である。
ドイツではこの点、古くから手立てが講じられてきた。有名なものは内部任用の禁止である。これは、教授任用は必ず外部からに限るという原則であり、たとえばその大学にすでに助手として在籍する者は、いかに優れていても教授候補にはなれない。内部任用禁止は法律にも規定があり、自己規律とばかりはいえないが、慣行として確立している。
厳格で入念なドイツの教授任用の手続き
ドイツの教授任用の手続きはかなり厳格で入念である。大学等で聴取したところをまとめると、おおよそ以下の手順である。なお、これは通常の任期なし雇用の教授職についての手順であり、任期付きの助教授の任用法はこれと異なる。
まず人事が始まるにあたって、そのポストがひきつづき当該学部に与えられるか、さらにそのポストで行われるべき教育・研究活動に変更はないかなどについて、参事会の承認が必要である。言いかえれば、現任者が辞めたからすぐ空きを埋める、とはならない。
参事会でゴーサインが出て人事開始となるが、それからが結構長い。任用手順が完了するまで最短でも1年半はかかる。加えて、後で述べるように、選考の過程では学内の他部署から種々のチェックが入る。もし、何らかの疑義が出され、その結果手順を繰りかえすことになれば、その分選考は長びく。2年、3年とかかることは珍しくない。
正式な手順が始まる前に準備的な作業を行うこともある。たとえばマックス・プランク協会は、専従のスカウト担当職員を使って、退職予定の教授ポストの候補者を数年前から国際的に物色する体制をとっている。