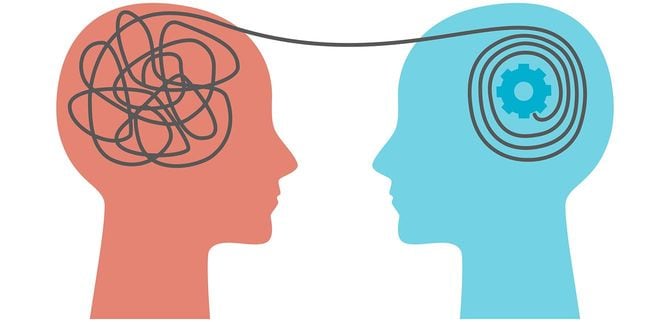※本稿は、和田秀樹『50代うつよけレッスン』(朝日新書)の一部を再編集したものです。
自己愛の満たされ方には3種ある
50代以降の人生では、自己愛が大切です。
「自己愛」というのは「自分が大事である」という心理全般のことですが、自己心理学の始祖であるハインツ・コフート(1913~1981)は、人の自己愛の満たされ方には3つの種類があると言いました。
一つは、人から褒めてもらうとか認めてもらうことによって自己愛を充たす「鏡自己対象転移」です。主に自分に注目してくれる親や養育者、つまり「鏡」のように自分を見てくれる存在が、その人の野心を育てます。
二つ目は、理想の対象を通して自己愛を充たす「理想化自己対象転移」です。
「偉い先生に診てもらっているから、自分は大丈夫」というように、自分が理想とする対象者に自己愛が支えられると転移が生じ、「自分はこうなりたい」という道標ができるのです。
そして「鏡」でも「理想」でも満たされない自己愛を支えてくれるのが、3つ目の「双子自己対象」です。
たとえば、誰かに褒められても、それは真意ではないと感じたり、理想対象のそばにいても、その相手にひがんでしまったり、自分のマイナス部分が気になってしまったりすることがあります。それは、「鏡」も「理想」も所詮、自分とは違う人間だと感じてしまうからです。
そもそも人間には、「他人と同じでありたい」とか「この人と同じ人間と思いたい」という根源的な欲求があるとコフートは述べました。人には、何でも話せてお互いを理解し合えると感じ、「この人は自分と同じ人間だ」と心から実感できる相手が必要なのです。それが「双子自己対象」です。
共感と同情の違いでわかる本当の仲間
「双子自己対象」をより具体的に述べると、気の置けない親友や、趣味を共有する仲間、自分と同じような立場に立っている人、同じような価値観を持っている人など、「この人と自分は同じ人間だ」と感じられる相手のことです。特にコフートは、「共感を覚える仲間がいるかどうか」が重要だと言っています。
「共感」と「同情」は似ているようで、実は極めて異なります。
同情も共感も、相手の感情を自分ごとのように追体験することですが、「同情」という表現は、相手が悲しみや苦しみなどのネガティブな感情を抱えているときに使います。
そして、どちらかといえば相手より心理的に上の立場に立ち、相手を「かわいそうに」と労ってあげる感覚です。ですから、失業したときや失恋したときなど相手が困窮しているときには同情しますが、相手が昇進したときや素敵な恋人ができたときには同情するとは言いません。
一方、「共感」はもう少し広い意味で用います。
相手が辛い目に遭ったときは一緒に悲しみ、相手が理不尽な思いをしたときには一緒に怒って、その思いを共有します。それだけではなく、相手に喜ばしいことが起きたときに一緒に喜ぶのが共感です。本当に仲のいい友だちの場合は、たとえば相手が出世したり、恋人ができたりすると、こちらまで嬉しくなります。