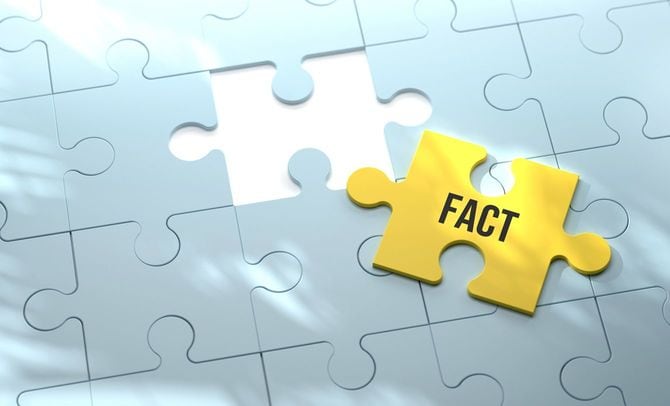科学の知を100%活用しない科学者たち
付言すれば、プラごみ問題に関するファクトを提供するはずの科学者側にも問題がある。
科学者の仕事は学術論文を書くことだ。転職にも昇進にも、その数がものをいう。そのとき、いちど社会に公表してしまった研究成果は、論文誌に掲載を拒まれるリスクがある。だから、いまこの社会に必要とされる成果が得られても、論文誌に載るまでは塩漬けになって利用されない。載ったころにはタイミングを逸しているかもしれない。
科学者たちは、そうした内輪の論理だけでなく、社会に科学の知を役立てることも考えるべきだという指摘は、30年まえからあった。だが、記事を書くため取材を申し込んでも、「論文誌への掲載が決まるまでは話せない」と断られることは、いまでもごくふつうにある。科学者コミュニティーの意識と習慣が変わらなければ、いま進行している社会問題の解決に科学の知を生かすことは難しいだろう。
このモヤモヤ感を無視してはいけない
レジ袋の有料化にまつわるこのモヤモヤ感は、きっと大切なものなのだ。思えば新型コロナウイルス禍でもそうだった。ファクトに基づかない突然の一斉休校。政策に都合のよい科学研究成果のつまみ食い。なぜそういう政策になるのか、筋の通った説明がない。ほんとうにモヤモヤした。
その時点でわかっている確かなファクトを公開し、数ある政策の選択肢のなかから、討議によってベストなものを選ぶ。その過程を透明にし、すべての市民の建設的な批判にさらす。それがこの社会に欠かせないことに私たちは気づいたからこそモヤモヤした。
「由らしむべし知らしむべからず」は、もうやめよう。モヤモヤは不快だが、忘れてはいけないのだと思う。