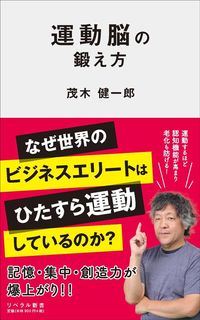チャレンジができなくなる口癖
たしかに、これは脳科学の観点からも合点がいきます。なぜなら、私たちの脳というのは、ある一定の標準をつくるプロセスにおいては、簡単にチャレンジできるようにできているからです。それがいまの若者にとっての、「いい大学に入る」「いい会社に就職する」といったことです。
ですが、一度その標準がつくられてしまうと、その標準こそが一般的で常識だと受け止めてしまう。つまり、そうした固定観念に何の疑問も持たなくなってしまうのです。これでは、脳のモビリティを高めることはできません。
そこで、現代社会を生き抜くために必要なのが運動IQというわけです。「普通は」「常識として」などといった口癖を持っている人たちは、自分のなかで勝手に常識の枠をつくり出してしまい、自分の限界を超えるチャレンジができないのです。だからこそ、多くの若者が苦労しているのかもしれませんね。
いくら知識や経験を蓄積しても、こうした自分本位の常識の枠というものが、運動IQを手に入れる阻害要因となってしまうことは、もはやいうまでもないでしょう。
自分を成長させるチャンスは無数にある
いま、私たちが生きている世界は不確実で、まだ知り尽くせないことがたくさんあります。さらに、AIが発展していく未来はなおさらです。それはつまり、まだそれだけのチャレンジが無数にあって、自分を成長させるチャンスがあるということでもあるのです。そういった発想の転換をするだけでも、新鮮な気持ちで自分の限界を超える意欲が湧いてくるはずです。
そこで必要になってくるのが、具体的にどのように動けばいいのかという、いわば運動IQを駆使するためのイメージトレーニングです。
それは、「ビッグになりたい」「自分の限界を超えたい」といった漠然としたことではなく、「これをやるには、自分はいま何をやるべきか」という具体的なイメージを持ってみることです。そして、そのイメージを持つことができたら、頭の中でシミュレーションをしながら全力でチャレンジしてみればいいのです。
なぜなら、自分の限界を超えるチャレンジをしたときにこそ、脳のモビリティは高まっていくからです。