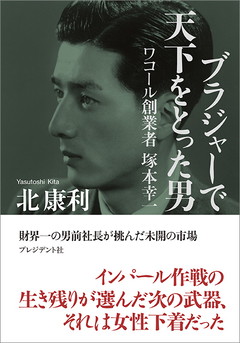「驚愕の報せ」で幸一は家を飛び出した
ところが9月27日の夜、驚愕の報せが届く。
「お兄さん、あの話あかんようになったみたいよ!」
仕事帰りに家に寄ってくれた和子が教えてくれたのだ。
知らない間に、ライバルの青星社が巻き返していたのである。難波の高島屋大阪店の推薦により、京都店への商品納入を決めていた。
複数社が納入できるはずはない。幸一の顔色が変わった。
「中川課長の家はどこや?」
と尋ねると、すぐさま家を飛び出していった。
中川の家を訪ねあてた時には、もうすでに夜の10時を回っていた。家の明かりも消えている。しかし、そんなことはおかまいなしに、戸をたたいて中川を起こした。
「こんな時間にどうしました?」
けげんな顔の中川に、幸一は真っ赤な顔で詰め寄った。
「聞けばほかに納入先が決まったというではないですか。一体どうなってるんです?」
激しい口調で不誠実を責めた。
幸一の勢いにたじたじとなりながら、中川はやっとの思いでこう口にした。
「上層部の判断だよ」
だが、そんな常套句の言い訳で納得できるはずもない。
「うちはお約束の日に納入できるよう一生懸命商品を作ってきたんです! それを商品も見ずに取引しないとは、あまりにひどい話じゃないですか?」
納得のいく説明をしてくれなければ、その場をてこでも動かない構えだ。
中川にも約束をたがえた後ろめたさがある。翌日、上司で雑貨第2部長の花原愛治に会わせようと言って、その場は引き取らせた。
一発逆転、ライバルとの決戦へ
だが幸一は知らなかったのだ、翌日、中川から事情を聞いた花原が、よしわかったと引き受けた上で、
「例によって、うまく断っておくから」
と告げていたことを。
雑貨第2部の担当範囲は、婦人雑貨のほかに靴、鞄、文具、玩具、時計、眼鏡、家庭用品、家具等と幅広かった。売れ筋は、傘、ショール、ハンドバッグなどである。初めて扱うことになった婦人下着は試しに置いてみるだけで、さほど期待してはいない。
まして新規開店のドタバタだ。どこの会社のものがいいとか吟味する暇もなく、たまたま本店から推薦があったのをもっけの幸いと、納入業者は青星社に決めてしまったというわけだった。
幸一は高島屋側の事情を知っていたわけではないが、絶体絶命のピンチから一発逆転を狙わねばならない状況であることは理解していた。
そして臆することなく一世一代の大演説をぶった。
花原は話を聞きながら思い始めた。
(この人はどんな商品でも売ってみせるという迫力がある。一旦決めた青星社を断ることは本店からの推薦があった手前できないが、両者を競争させてみるというのはありかもしれん)
そして思案した揚句、
「では1週間だけテスト販売の期間をさしあげよう」
と譲歩案を示してくれたのである。
要するに青星社と販売競争をやってみろというのである。
「望むところです!」
幸一は深々と頭を下げた。