マッキンゼーは撤退寸前だった

『企業参謀』という表題は私が自分で考えた。なぜ「企業参謀」だったのか。それは当時の日本のコンサルティング業界が置かれていた状況に由来する。
当時、私は30歳そこそこ。ビジネスの相手は60歳を超えたトップや経営陣である。「お幾つですか?」と尋ねられて正直に言おうものなら、大方、「なんだ、まだハナタレ小僧じゃないか。それが社長のオレにアドバイスだと?」という空気になる。
その時代のコンサルタントと言えば、大会社を勤め上げた白髪の老練と相場は決まっていた。皺に刻んだ自分の経験を現役の経営者に口伝して月々20~30万円のお手当てをもらう。そんなイメージである。
さらに言えば、当時の日本社会では、「コンサルタント」という言葉自体に、どこか怪しげな商売という響きが付きまとっていた。クライアントからすれば「自分の会社のことは自分たちが一番よく知っている」というのが常識的な考え方だった。
業界に入ってまだ1、2年のハナタレと知れたら、まず信頼してもらえない。そこが最大の悩みだった。だから年をなるべく聞かれないように気を付けたし、聞かれたら話題を変えたり、とにかく苦労した。
あの頃、若松茂美(のちマッキンゼー ディレクター。現一橋大学非常勤講師)などと一緒に500社ぐらいのドアを叩いただろうか。提案書を書いて持っていくと、当時の日本はまだアグレッシブだったから、「これは素晴らしい」「ウチの会社もこういう戦略が必要だ」なんて反応がたまに返ってくる。
しかし提案書の最後に書いてあるフィーを見て、大抵、相手は引きつった。
「これ1年分の間違いじゃないの?」
白髪のコンサルタントがどんなに高くてもせいぜい月50万円の時代に、月額2500万円などという破格のフィーが書き込まれているのだ。しかも目の前にいるのは自分よりはるかに年下の若造である。このギャップは相当に大きかった。
私個人だけの問題ではなかった。コンサルティングの価値が理解されていない状況では、いくら戦略提案しても受け入れてもらえない。
あるとき東京支社長に呼ばれてこう言われた
「ケン、お前は優秀だ。東京事務所を閉めることになったら、サンフランシスコが欲しがっていたから、そっちへ行ってもらう」
マッキンゼー東京事務所の業績は振るわず、撤退寸前まで追い込まれていたのである。

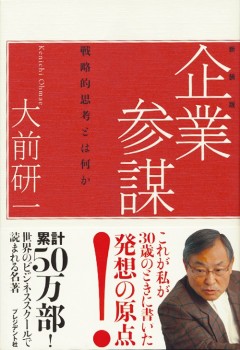
![企業参謀ノート[入門編]](https://presidentstore.jp/client_info/PRESIDENT/itemimage/002018-s.jpg)



