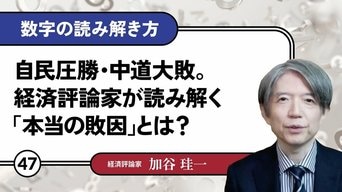九州・中部地方を中心とした豪雨では、自治体が定める浸水エリアから外れ、河川から離れた建物も多くの被害を受けた。不動産コンサルタントの長嶋修氏は「こうした立地にもかかわらず浸水した一戸建てには、大まかに3つのタイプがある」という――。
浸水エリア外でも多くの建物が被害に
令和2年7月豪雨は、熊本県を中心に九州・中部地方に大きな被害をもたらした。とりわけ熊本県では24時間雨量が「多いところで200ミリ」としていたところ(気象庁)、実際には400ミリを超える雨量となるなど、全国で75名の死者を出している(消防庁、7月15日午前6時30分時点)。
浸水リスクゼロのエリアを選ぶのがベストだが、大きな河川が近くを流れる街などでは、リスクゼロの土地を探すのは難しい。自治体によるハザードマップの確認や、万が一の備えへの重要性が改めて浮き彫りになった形だ。
忘れてはいけないのが、浸水のなかったエリアでもこうした豪雨の中では多くの建物が被害を受けていることだ。これまでの被害事例を、主に一戸建てについてご紹介する。
1.「基礎の低い家」は床下浸水しやすい
ハザードマップで浸水の可能性が指摘されているエリアでは、都心部・都市部の狭小地に建つ3階建てに多い「基礎の低い家」が、最も水害のリスクが高い。半地下を設けた一戸建てと同様、建物の高さ制限を守ることを目的として、あるいは高齢者に配慮し、バリアフリーの観点から、建物の「基礎」を低くしている一戸建ても多く、水害のリスクが高い構造の典型例だ。
地表面からの基礎の高さは、40センチ以上取ることが望ましいとされているが、建築基準法で定める下限の高さは30センチ。そのため、基礎高が40センチに満たないケースも珍しくない。筆者が創業したさくら事務所が調査した住宅では、後から設置した花壇が原因で、地表面の高さが上がり、基礎高が10センチ程度しかない状態で、ゲリラ豪雨の際に床下浸水の被害を受けた。もし花壇を作らなければ、被害を受けずに済んだはずだ。