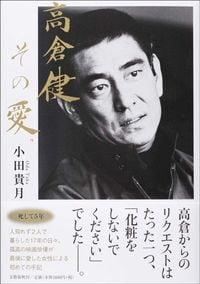春は鶯、夏は線香花火、秋は小鳥と“一騎打ち”
たとえばこうだ。
2階にある3つの小部屋は衣類専用で、南極、北極対応のダウンも毎年のように増えていった。1階の床下収納には寝袋が20枚近く整列していた。
一人だったときは、朝は自分で珈琲を淹れる。スポーツジムに行って、フルーツをジュースにしてもらって飲んだり、腹が減って我慢できなければ、カロリーメイトをつまんだりしていたそうだ。
東映を離れてフリーになってからは、一時期サプリメントに凝って、店を出そうかと真剣に考えたことがあった。
ロケに行くときは、薬屋が引っ越すほどの量を用意した。アルコールは一切やらない。タバコも映画『八甲田山』の撮影の時にやめた。
料理と飲み物は常温か暖かいもの。肉食第一主義で、魚類は好まないが、外食でのすしは例外。
子どもの頃は虚弱体質で、8歳の時に肺浸潤(結核の初期)にかかり、1年間休学した。心配した高倉の母親は、兄妹3人の食事とは別に、毎日鰻を食べさせたという。そのため長じてから鰻は食べなかったそうだ。
江利チエミが急逝すると、いろいろなことが嫌になって海外へ完全移住しようとしたことがあった。移住先は「ご飯をとれば香港。ハワイは何てったって風だね」。私も同感である。
四方をモチノキや白樫の木々に囲まれ、絶対にのぞかれないようにした家の中では、このような暮らしをしていたそうだ。
「春の訪れは、鶯の幼鳥の鳴き声に告げられ、夏は庭のベッドで海水パンツ日光浴。夜風に吹かれ、愉しんだ線香花火。秋にはピラカンサ(トキワサンザシ)の熟れた実をついばむ尾長に、玩具の銃を手に一騎打ちに挑み、初冬、落ち葉のあまりの量の多さを見かねて、思わず箒を手に加勢してくれた奇跡の落ち葉掃き」
「家政婦は見た」にふさわしいレシピの豊富さ
この本の中で、丹念に書き込まれているのは食事のことである。たとえば、亡くなるまで欠かさず食べていたというグリーンサラダについて、
「葉物の主役はルッコラ。それにレタス、ロメインレタス、サラダ菜、アンディーブ、白菜、などから三、四種類をミックスします。さらに季節によって、マンゴー、メロン、洋ナシ、林檎、葡萄、無花果などの果物を盛りつけ、胡桃、松の実、アーモンド、ビスタチオ、カシューナッツ、ヘーゼルナッツなどから、数種類をトッピングします。ドレッシングは、エキストラバージンオリーブオイルと、イタリア・モデナ産二十五年もの熟成バルサミコ酢、醤油を隠し味に数滴加え、挽きたての黒コショウをブレンドしました」
その他にも、中華メニュー、イタリアンメニューなどの作り方にもかなりのページを割いている。
私が「家政婦は見た」とタイトルを付けたいと考えたのが、おわかりいただけるだろう。
『週刊新潮』(11月14号)で、貴月の義理の母親・河野美津子(86)が、貴月の3度の結婚歴を明かした後、こう語っている。
「詳しい事情は何も知りませんが、健さんにとって貴さんは家政婦だったということでしょう。健さんは、江利チエミさんが亡くなった時、“彼女以外を愛さない”という風に言っていたんでしょう。私は健さんを信じています」
食事のレシピや映画についての記述に比して、高倉健との出会い、どうして一緒に暮らすようになったのか、高倉健の亡くなる時の様子などは、さらっと触れているだけである。