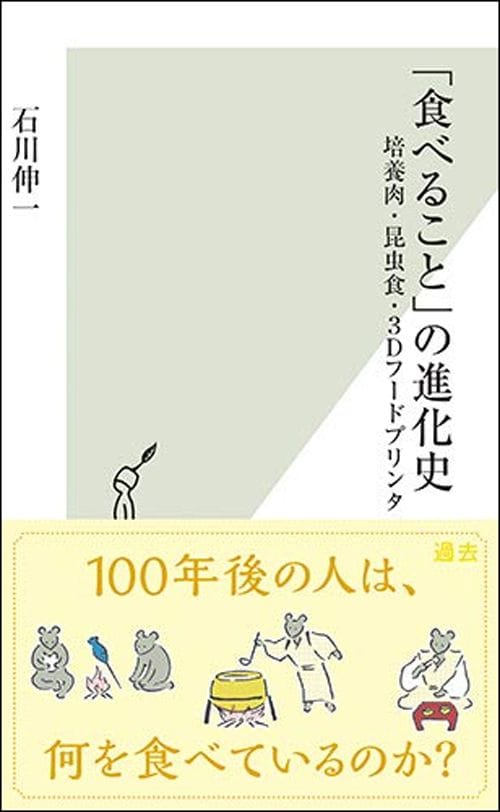「ひとり食卓」が日常化している
現代の一般家庭で、神棚や仏壇に食べものを供えるのは、ご年配の方のいる家庭が主となり、家庭の食卓で、神や祖先との聖なる行事としての共食は消失しました。私たちは、かつて祭りのときにしか食べられなかったごちそうやお酒を日常的に食しています。
家族といつも一緒に同じものを食べるという家庭も一般的ではなくなり、各個人がそれぞれの都合に従って食べる「ひとり食卓」が、現代の日常の「ケの日の食事」の傾向としてあります。家族がそろって食べるようなお正月などの「ハレの日の食事」が、昔でいう神と食べた祭りの食となっています。
そもそも、家族と一緒にものを食べる共食は、家族内のコミュニケーション上、重要な行為なのでしょうか。
共食は家族関係を良好にするか
前述した表氏の調査によると、乳児を持つ家庭には、家族との食事の共有と家族関係との間に関連は認められませんが、大学生の子どもと同居する家庭では、家族そろった夕食の頻度が高い方が、家族のまとまりに好影響がみられることが明らかにされています。また、小学生を対象とした調査によると、食事中の家族との会話は、子どもの健康に良い影響を及ぼすことも報告されています。
中学生に関しては、食卓が「安らぎの場」と思える場合に限り、家族との食事は登校忌避感などを低下させる要因になっています。条件つきなのは、中学生は親子間の葛藤が起こりやすい思春期の時期にあること、親子の会話に学校の成績や進路に関する話題が増えることなどから、家族そろって会話をしても中学生にとっては「心安らげない」食卓が存在する場合もあるためです。
当然ながら、人はただ共食をすればお互いの関係が深まるものではなく、一緒に何をするにせよ、意見を伝え合い、理解する気持ちがあるかが重要なのでしょう。
近年の子どもたちをめぐる問題は、家族内コミュニケーションと結びつけて論じられることが数多くあります。個人個人の時間が増えている現代の家族にとって、食卓での共食は親子のコミュニケーションを深める場として期待されています。しかし、共食という行為だけをとらえて過剰に期待するのには用心しなければならないでしょう。
宮城大学食産業学群教授
1973年、福島県生まれ。専門は分子調理学。東北大学大学院農学研究科終了後、日本学術振興会特別研究員、北里大学助手・講師、カナダ・ゲルフ大学客員研究員などを経て現職。著書に『料理とのおいしい出会い 分子調理学が食の常識を変える』(化学同人)、『必ず来る!大震災を生き抜くための食事学』、共訳著に『The Kitchen as Laboratory 新しい「料理と科学」の世界』(講談社)など。