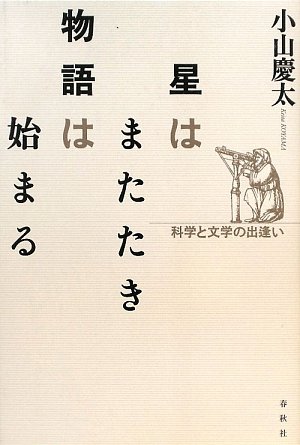著者は早稲田大学教授で科学をわかりやすく伝えるサイエンス・コミュニケーションの第一人者である。本書は副題に「科学と文学の出逢い」とあるように、小説・エッセイ・映画などを科学者の目で楽しむ理系の文学論である。
なかには50作以上の作品が取り上げられている。たとえば、ネス湖の巨大生物ネッシーを題材にした映画『ウォーター・ホース』を用いて生態系を語り(34ページ)、池澤夏樹の文学書『星に降る雪』から素粒子ニュートリノの最新天文学を導き出す(64ページ)。スピルバーグ監督のSF映画『A.I.』に描かれた人工知能を紹介しつつ、ノーベル賞学者ローレンツの名著『ソロモンの指環』の刷り込み理論を絡ませてゆくあたりは、著者ならではの見事な切り口である(125ページ)。
科学のアウトリーチ(啓発・教育活動)に役立つ逸話だけではない。原子爆弾を生んだマンハッタン計画に関わった物理学者ファインマンが、結核で先立たれた妻と交わした純愛物語に涙を流さぬ読者は、いないのではないか(160ページ)。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント