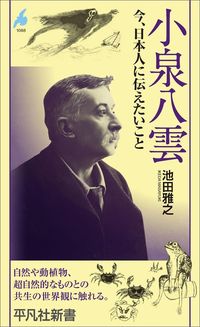残忍な「殺人事件」取材記事で人気を呼ぶ
八雲はこの都会を「獣のごときシンシナティ」あるいは「実利一辺倒の豚肉詰めのシンシナティ」(『アメリカ雑録』)と悪態をつきながらも、薄汚く悪臭の漂うこの都会でみずからの活路を見つけようとあがいていました。
アメリカに着いてから5年後の1874年に、転機が訪れました。八雲24歳の時でした。詩人テニスンの「王の牧歌」について書いた八雲の持ち込み原稿が、「シンシナティ・インクワイヤラー」紙の主筆ジョン・A・コカリルの目に止まり、同紙の定期的な寄稿者となることができたのです。
しかし八雲が事件記者としての評判を勝ち取ったのは、なんといっても1874年11月9日に「インクワイヤラー」紙に掲載された「皮革製作所殺人事件」という犯罪記事でした。この記事は、フライベルグ皮革製作工場で皮なめし職人のハーマン・シリングが、エグナー父子と同僚のジョージ・ルーファーの3人に暴行を受けたうえ、六ツ叉のフォークで突き刺され、工場の炉のなかに押し込められたまま、焼き殺されるというきわめて残虐な殺人事件を扱ったものでした。文面があまりに生々しくグロテスクなので、一読すると辟易してしまいますが、その記事のさわりの部分を引用してみましょう。

ここから先は無料会員限定です。
無料会員登録で今すぐ全文が読めます。
プレジデントオンライン無料会員の4つの特典
- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信
- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能
- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能
- 記事をブックマーク可能