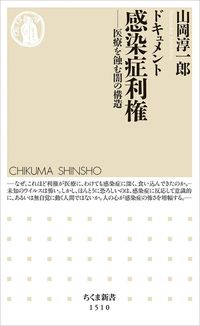三度の流行で、38万人以上が死亡した
客船内の感染爆発に、政府のマスク配布、大病院の診療拒否による患者の死亡、と100年後の新型コロナ禍でも同じことが反復される。社会は進歩しているのだろうか。
被害が甚大なのは、当時の医学ではインフルエンザの病原体、ウイルスの存在が解明されておらず、ワクチンも治療薬もなく、患者の隔離も不徹底だったからだ。ウイルスの発見は1931年の電子顕微鏡の発明後まで待たなくてはならなかった。
もっとも、患者の鼻腔粘液や喀痰からは何種類もの細菌が分離されており、そのうちのどれかがインフルエンザ菌だと医学者は考えた。新設の北里研究所は、分離される割合の高かったパイフェル氏菌を病原体と断定し、その菌でワクチンをつくる。対抗する東京帝大伝染病研究所は、病原体を確定しないまま「予防液」としてパイフェル氏菌と肺炎双球菌の混合ワクチンをこしらえ、発売にこぎつけた。互いにわがワクチンこそ効力が高いと論争をくり広げる。当時からワクチンは研究所の利権だった。
どちらのワクチンもウイルスとは無関係だから、虚しいバトルではある。しかしながらワクチンは約20万人に投与され、発病は阻止できなかったけれど死亡率を下げる効果はあったともいわれる。重症化による細菌の二次感染を防いだのだろうか。内務省衛生局が編集した『流行性感冒「スペイン風邪」大流行の記録』は、1918年8月から21年7月までの三度の流行で日本では38万8727人が亡くなったと記す。人口学者の速水融は死亡者数を約45万人と推定している。