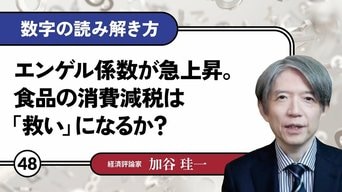国内従業員の1割強が「早期退職」の対象に
化粧品業界最大手の資生堂が苦境に陥っています。化粧品業界はコロナ禍の影響で2020~22年に売上高を大きく減らしており、23年12月期決算では大幅な回復が期待されていました。ところが中核を担う日本事業は売上高2599億円で、コロナ禍前の19年12月期の4515億円と比べると6割程度でした。
一方、「コア営業利益」は18億円と前年に対して149億円改善し、黒字に転換しました。しかし、19年度の営業利益は910億円。22年12月期第1四半期から国際会計基準であるIFRSを採用しているため、単純比較はできませんが、回復の遅れが読み取れる結果となりました。
これに危機感をもったのでしょう。資生堂は2月、1500人の早期退職募集を発表しました。資生堂の国内事業の従業員は、本部機能を除くと約1万3000人で、今回の早期退職募集は1割強にあたります。
筆者は、資生堂が苦境に陥った原因として、「戦略の3つの誤り」があったとみています。
1つ目は、若年層をつかみ損ねた長期戦略の舵取りミスです。歴史的にみれば、高度成長期からバブル期にかけて、百貨店などの大型店舗や街の専門店を足場として商品の値崩れを防止することでブラント構築をしてきた同社ですが、その過去の栄光が影響したのか、新たな潮流への対応力に欠けたといえます。
化粧品販売の「黄金セオリー」が崩された
その典型例としてあげられるのが、2000年代にドラッグストア、コンビニエンスストアなどで展開されてきた「プチプラコスメ旋風」への対応の遅れです。プチプラコスメとは、プチ(petit=仏語で少し)とプライス(price=英語で価格)を組み合わせ、手軽で安価な化粧品という意味を持たせた造語です。
同時にEC(電子商取引)対応の遅れという、戦略的ミスも指摘できます。「化粧品は対面で売ってこそ顧客満足度が高まる」という黄金セオリーが、もろくも崩されてしまったのです。
以前は百貨店詰めの美容部員や研修を受けた化粧品店員が、化粧ノウハウを伝授することがウリとなっていた化粧品販売も、今やそのノウハウはYouTubeなどからタダで手に入れられる時代となりました。その結果、化粧品はECサイトやドラッグストアで簡便かつ安く手に入れるのが、若い世代の常識となってきたのです。