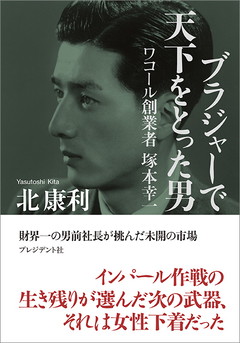「生き残ってよかったのか…」自問自答の日々
そして迎えた終戦。その報せを塚本幸一は、タイの首都バンコク近郊の集結地バンボンで聞いた。その瞬間、泣きだす兵士もいたし、自決する者も出た。だがほとんどは、ただ茫然とするばかりだった。
(どの面さげて内地に帰れというのだ……)
という思いがなかったわけではない。
しかし、戦う理由がなくなった今、死んでどうなるものでもないという思いが、生き残った者ほとんどの共通した思いであった。
終戦の年の10月、武装解除された。
そして昭和21年(1946)5月末、幸一たちはバンコクに集められ、ようやく復員船で祖国に戻れることとなった。
生き残ったことを幸運として喜べる無神経さを彼は持ち合わせていない。復員船の甲板から油のような南洋の海を眺めながら、
(本当に俺は生き残ってよかったのか……)
そればかりを繰り返し自問自答していた。
身体から何か大切なものをごっそり削ぎとられ、心はすっかり干からびてしまっている。そんな状態のまま、果たして生きていくことができるのか……いや、生きていていいものなのか。
出航して3日目のこと、いつものように波頭を照らす日の光をぼんやり眺めていた時、ふとある考えが頭をよぎった。
(俺は生きているのではなく、生かされているのではないか? それがどれだけ心の重荷になろうが、死んでいった戦友の分まで生きていかねばならないのだ)
そう悟った時、その重さが逆に彼の心を軽くした。
(それならば、生きて帰っても許してもらえるかもしれない……)
そう思えたからだ。
トコロテンの値段は戦前の200倍に跳ね上がった
「日本だぁ! 日本に帰ってきたぞ!」
陸地が遠目に見えてきた瞬間、兵士たちの間からすすり泣きの声が起こり、幸一もまた甲板に並んでいる他の戦友たち同様、滂沱の涙に頬を濡らしていた。
昭和21年6月12日の夕方、復員船は浦賀港に入港する。その翌日、5年半ぶりに、夢にまで見た祖国の土を踏んだ。
だが感傷的な気分に浸っていられたのはそこまでだ。ノミやシラミがたかっているというのでDDTの白い粉を頭からかけられ、我にかえった。
「よし、次!」
内地で除隊になった兵隊は、持てるだけの米や毛布を持って帰らせてもらえたようだが、幸一たちは5年7カ月の兵役の報酬として720円を支給されたほかは、身の回り品を入れるための麻袋とマラリアにかかっていた時のために特効薬のキニーネを1本渡されただけだった。
驚いたのが物価の高さだ。
上陸してすぐ浦賀の町で食べたトコロテンが10円もしたのには仰天した。戦前なら5銭ほどだったから200倍だ。
すさまじいインフレを前にして、激しい焦燥感にかられた。