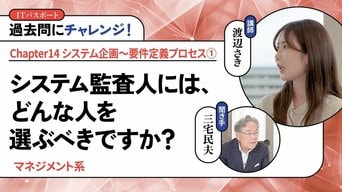コロナ禍で多くのファッションブランドが苦戦している。ジャーナリストの川島蓉子さんは「コロナ禍でも売れているブランドはある。その違いは、消費者の変化を敏感にとらえ、業界の古い常識から脱却できたかどうかだ」という——。
※本稿は、川島蓉子『ブランドはもはや不要になったのか』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。
「ファッションへの関心は薄まる一方」は本当か?
街を歩いていると、閉店した店に目が行く。路面店だけでなく、ファッションビルやモールの中でも、シャッターを下ろしているショップが目立ち、撤退したのは飲食店だったのかアパレル店だったのか、書店だったのか、思いを馳せることは少なくない。コロナ禍で拍車がかかった現象だ。
またコロナ禍以前より、アパレル業界については、老舗百貨店やセレクトショップ、ファストファッション企業の経営不振が数多く取り上げられている。その文脈の中に、「人はものを買うこと、所有することに意味を感じなくなっている」、「ファッションに対する関心は薄まる一方」、「ブランドに価値を感じるのは限られた人だけ」といったものも含まれているのだが、本当にそうだろうか。外出が減り、ハレの場が減った私たちの物欲は、なくなったのだろうか?
先日、ルームウエアで人気が高い「ジェラート・ピケ」をはじめ、若い女性に人気の「スナイデル」、「フレイアイディー」などを展開しているマッシュホールディングスでこんな話を耳にした。
「以前から抱えていた課題について、コロナ禍を契機に、社内の意識改革と戦略転換を一気に進めた。ECに力を入れてリモート接客を進めたところ、お客からの反応は良好。リアル店舗についても、不採算だから撤退という判断ではなく、過剰だった店舗のあり方を見直した。それも効率が悪いから閉めるという判断でなく、有用と思われるところへは、新規業態の開発や出店を進めている」