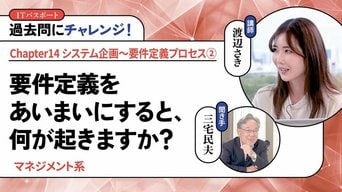20世紀初頭のウィーンで活躍した画家エゴン・シーレ。彼はたくさんの若い少女たちをナンパし、アトリエに連れ込み裸体を描いた。その結果、誘拐容疑で投獄された。アートディレクターのナカムラクニオ氏は「彼は、タブーとされた性の表現を強調すればするほど、純粋な精神に近づくと考えていた」という――。
※本稿は、ナカムラクニオ『こじらせ美術館』(ホーム社)の一部を再編集したものです。
「自分はゴッホの生まれ変わり」
エゴン・シーレは駅で生まれ、超特急のような人生を送った。
官能と享楽を求めたこの画家が描く線は、どこまでも走り続け、誰にも止めることができなかった。彼は、スピードとスリルをエネルギーにして生きた画家だった。
1890年6月12日、シーレは、オーストリアのドナウ河畔にある小さな町、トゥルンの駅で生まれた。父アドルフが国有鉄道に勤める駅長だったため、駅の2階が一家の住まいだったのだ。1890年といえば、ちょうどゴッホが死んだ年。そのためシーレは、生涯にわたり「自分は、ゴッホの生まれ変わり」と考えていたらしい。
父アドルフの出身は、北ドイツ。家系には政治家、軍人、法学者などがいて、14世紀までさかのぼる名家だった。一方、母は南ボヘミア(現在のチェコ)のクルマウ出身。農民や職人の家系だが、父が鉄道関係の建築業で財を成し、ウィーンに貸家を6軒も持つほどの資産家だった。そんなシーレ少年の楽しみは、汽車から降りて行き交う人々を見つめながら、絵を描くことだった。ウィーンに向かう、あるいはやってくる人々が乗り降りするホームで、彼は人々と汽車を眺め続けた。8歳頃のスケッチが残されているが、やはりそこには汽車が素早いタッチで描かれている。