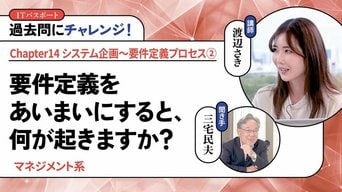※本稿は、マーティン・ファクラー『日本人の愛国』(角川新書)の一部を再編集したものです。
「日本兵のお守りを遺族に返してほしい」
戦中の狂信的な愛国は、戦後、どのように変化したのだろうか。それを感じた私の個人的なエピソードとともに紹介したい。
時は2003年にさかのぼる。当時私はウォール・ストリート・ジャーナル紙の東京支局で働いていた。ある日、自宅に突然送られてきた手紙に大きな衝撃を受けた。送り主は私の祖父の従兄弟(以下、大叔父と記す)で、当時80歳を超えていた。そこには、大叔父が太平洋戦争中の硫黄島の戦いに兵士として参戦したこと、死亡した日本兵のお守りをアメリカへ持ち帰っていることが記されていた。
そして、遺品であるお守りをどうにかして遺族に返してほしい、とあり、そのお守りが同封されていた。
大叔父とはアメリカにいるときに幾度となく会ったことがあった。知っていたのは、彼がアイオワ州の田舎の農場で育ち、18歳のときに徴兵され、いきなり遠い太平洋に行かされたこと、聞いたことのない島で会ったことのない異国の敵と戦ったこと、などだった。戦争での具体的な体験については沈黙を守っていたので、硫黄島で戦っていたことは初耳だったし、日本兵のお守りについてもこの手紙で初めて知った。
想像するだけで悲しい気持ちが込みあげてきた
戦いから半世紀以上が過ぎていた。自責の念に駆られながらも、だれにもいうことができず、胸中に封印してきたのだろう。大叔父がアメリカ海兵隊でどのような師団に所属し、硫黄島のどこで戦ったのかは詳しくはわからない。抱いてきた苦しみはどれほどだったのだろうか。
想像するだけで、悲しい気持ちが込みあげてきた。戦争は人間を狂気に駆り立てる。時間が経過していくなかで大叔父は、戦地へ赴いたアメリカ兵と日本兵に、敵と味方ではありながらも、共通点を見出だすようになったのかもしれない。
戦争の目的こそ日米の間で違っていたものの、実際に硫黄島で戦火を交えた日本兵たちに罪があったとは思えなかったのだろう。彼らもまた母国のために、悲壮な思いを背負って戦っていたからだ。
しかし私は、受け取ったお守りを見て途方に暮れた。「不動明王」という判が押された極めて簡素なものだったからだ。持ち主の名前はもちろん、地名や寺院名などはなにも記されていない。
おそらくは戦時下の日本で大量生産され、戦地へ赴く日本兵へ、日本軍から、あるいは家族から手渡されたものだろう。大叔父は日本語が読めなかったが、日本に住んですでに7年を迎えていた私ならば何とかしてくれるだろうと考えて、送ってきたのだと思う。高齢となった大叔父はそのころ体調もよくなかった。その年齢に至るまで心にしまっていたのかと思うと何とか思いに応えたい、という気持ちが募った。