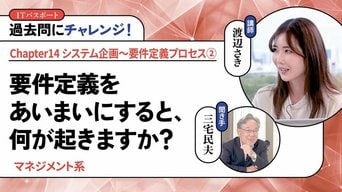お産は国や歴史的な経緯によって変わる「文化」
【髙崎】アメリカでは分娩の約7割、フランスでは経膣分娩の約8割が無痛分娩、つまり麻酔のもとでお産をしていますが、日本ではその数字は分娩の1割にも満たない6.1%(2016年。日本産婦人科医会)です。なぜ日本では、無痛分娩が普及しないのでしょうか。
【海野】無痛分娩の話をする前に、大前提として確認したいことがあります。それはお産が、国や歴史的な経緯によって変わる文化的な営為だということ。「お母さんが安全にお産をして、赤ちゃんが無事に生まれてほしい」という願いは人類全体で共通しているはずですが、実際の方法は国によって、民族によって、文化的背景によって異なります。日本では当たり前のことが、世界では全然一般的とは言えないこと、日本のお産のあり方は、他国とは大きく違っていることを知る必要があります。
人間のお産自体は原始時代からずっとあり、20世紀の前半まで、世界的にはそれほど差はありません。自然に生まれてくるお子さんと産むお母さんを助ける「助産」が中心です。お産が大きく変わったのは、19世紀の半ば。今の医学の基盤となっている概念ができた頃からで、鉗子分娩や帝王切開などの医療介入が始まりました。笑気やエーテルを用いた麻酔術もこの頃から行われ、お産にも使われました。
お産には、非常に強く苦しい痛みがあります。陣痛は非常な激痛を伴うからです。それに対して麻酔を使おうと、無痛分娩が始まったんですね。ただ麻酔は医療介入ですから、「医療体制がないところではできない」という大前提があります。安全に麻酔を提供できる環境がなければ、当然ですが、無痛分娩も発展しません。
またお産という生理現象自体は、麻酔が無くてもできる。私は無痛分娩の推進派ですが、必要ないだろうという考えの方々は、日本には、一般の方の中にも、専門家の中にもたくさんいます。無痛分娩の導入には、妊婦さんのニーズと、麻酔を提供できる体制かどうかが影響する。加えて、「無痛で産むこと」が社会でどう受け入れられるかが、関わってきます。
このようなお産のあり方という点と、お産に対する考え方という点が、これまで日本と欧米では大きく異なっていたので、その結果として無痛分娩の普及率も違ってきているんです。
欧米と日本のお産は「分娩施設の規模」が違う
【海野】欧米と日本のお産ではまず、分娩施設の規模の違いがあります。アメリカでもヨーロッパでも、分娩は1カ月に数百件を行うような大規模な医療施設が基本。お産には命に関わる緊急局面があるので、いつでも医療介入できるよう、大規模施設でしなくてはならない、という考え方です。大規模分娩施設では、緊急手術に対応するため、通常、常勤の麻酔科の先生もいます。そういった施設にとっては、無痛分娩は「もともとそこにある麻酔の資源を投入するもの」ということになります。