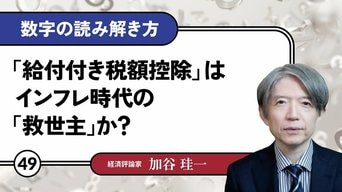幸福感は意外と各国で共通

大阪大学社会経済研究所 教授 大竹文雄●1961年、京都府生まれ。京都大学経済学部卒業、大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。大阪大学博士(経済学)。『日本の不平等 格差社会の幻想と未来』でサントリー学芸賞を受賞。ほかの著書に『経済学的思考のセンス』『競争と公平感』などがある。
「ご自分のことを現在、どの程度幸せだと思いますか」
この問いかけに、あなたはどう答えるだろうか。内閣府が毎年行っている「国民生活選好度調査」では、「幸せである」「どちらかといえば幸せである」「どちらかといえば不幸である」「不幸である」の4段階で回答してもらい、経年変化を調べている。
こうした調査結果が「幸福度」と呼ばれる指標だ。そして、所得水準や消費動向、家族形態や失業といった様々な要素と幸福度との関連性を追究するのが、「幸福の経済学」である。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント