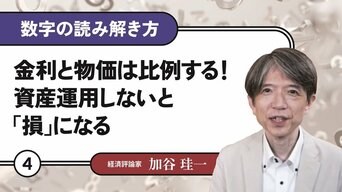大腸がんと診断されて知った「事実」
日本人の2人に1人ががんになる時代……だが、がん治療によって「妊孕(にんよう)性=子供を作る機能」が喪失する可能性があることを知っている人はどれくらいいるだろう。少なくとも4カ月前、35歳で大腸がんと診断された筆者はこの事実をまったく知らなかったため、治療の合間に情報収集や対応に奔走することになった。
医療技術の発展によってがんが克服可能な病となってきた今だからこそ、若きサバイバーたちの“その後の人生”をどう支援するかが重要な課題になっている。
そんな中、2012年に「日本がん・生殖医療学会」を立ち上げ、この問題にいち早く取り組んできたのが、聖マリアンナ医科大学の鈴木直教授だ。鈴木氏は日本で卵巣組織凍結をいち早く成功させた“妊孕性温存のエキスパート”であるが、あくまでも最優先は「がん治療」と語る。その真意と、若年層がんの今を聞いた。
40歳未満では年間2万3000人が「がん」に
――将来子供を持つ可能性のある若年層のがん患者は増えているのでしょうか。
39歳以下のがん患者、いわゆる小児・AYAがんの統計が昨年初めて国立がん研究センターから発表されました。それによると、推計で年間約2万3000人の39歳以下が新たにがんに罹患しているとされています。昨年の夏以降、国がこの世代のがん患者さんの医療の充実に乗り出すことが明らかになり、やっと顕在化してきたと言えるでしょう。
またさまざまな関係者が尽力した結果、昨年3月、国の第3期がん対策推進基本計画の中に「小児がん、AYA世代(※)のがんに対する医療の充実」という文言が入りました。これにより、進学・就職・結婚・出産といったライフイベントが控える若年がん患者に対する、さまざまな支援が拡充していくことが期待されます。
※AYA世代とは、「Adolescent and Young Adult/思春期・若年成人」を指す
――私は大腸がんになるまで、「がん治療によって子供が作れなくなるかもしれない」ことを知りませんでした。自分の知識のなさに輪をかけて困ったのが、医療従事者から詳しい情報が得られなかったことです。医療機関や医師によって情報に幅があるのはなぜでしょうか。
妊孕性温存は、小児・AYA世代のQOL(生活の質/quality of life)を上げる大きな一要素です。にもかかわらず00年代の初頭まで、がん患者の生殖医療に関して医師たちの間に共通した指針や方針がありませんでした。がん治療の主治医と不妊治療を行う生殖医療医との連携もなかったため、妊孕性温存の機会を損失してしまうケースすらあったのです。そういった状況を打破し、患者さんに的確なタイミングで正しい情報を伝えたいという思いから、12年に「日本がん・生殖医療学会」を作りました。