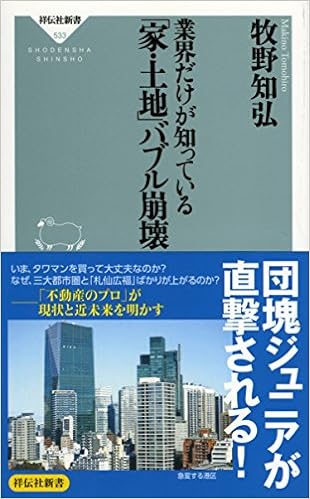これから立ち上がるのは“巨大航空母艦ビル”
東京都心のオフィスマーケットが好調だ。三鬼商事の調べによれば2018年5月現在、東京都心5区(千代田、中央、港、渋谷、新宿)のオフィスビルの空室率は2.68%。空室率が4%を切れば完全な「貸し手市場」と呼ばれるマーケットで、この水準はやや異常とも思われる逼迫状態だ。
先日竣工した大規模新築ビル、日比谷ミッドタウンも旭化成グループをアンカーテナントに迎え、オフィス部分はほぼ満室、順調な滑り出しだという。東京都内はオフィスビルの建設ラッシュだ。森ビルの調査によれば、2018年から五輪が開催される2020年までの3年間に都内では75棟、面積にして約413万平方メートルの大規模ビルの供給が予定されている。大規模ビルとは森ビルの定義によれば1棟の床面積が1万平方メートル(約3000坪)以上のビルを指す。これから東京五輪開催までに年平均で138万平方メートルのオフィスが都内で新たに誕生することになる。
この年間138万平方メートルという供給量は、平成バブル期と言われた平成初期の頃の供給量であった年間100万平方メートルを凌駕する大量供給だ。さらに平成バブル期と異なるのは供給棟数の違いにある。
1989年から91年までの3年間のオフィス供給量は312万平方メートルで、棟数は117棟にも及ぶ。つまり、平成バブル期は1棟平均2万6660平方メートル(約8060坪)だったビルの規模が、今後3年間で建設されるビルは平均で5万5000平方メートル(約1万6640坪)と約2倍の規模に膨らむことになるのだ。
特徴的なのは、今後5年間で供給が予定されているビルの約70%が都心3区(千代田、中央、港)で建設が予定されていることだ。また同じく森ビルの発表によれば、都心3区で新たに供給される予定のオフィスビルのうち約70%相当が、既存ビルの建替えによるものだという。
つまり今後、大量供給は予定されているものの、その中身は老朽化した既存ビルの建替えが中心であるから、オフィス床が大量に余ることはなく、市場では十分に吸収できるというのが多くの業界関係者の見方だ。
さらに国や東京都では、今後、東京をアジアの国際金融センターにする構想も喧伝されている。東京に多くの外資系金融機関を呼び込むために、国家戦略特区を設定し、法人税の減免や会社設立手続きの簡素化、外国人メイドなどの受け入れなどを認めるといった趣旨で制度整備を行ない、外資系金融機関を東京に誘致しようというものだ。
しかも、これから都心で立ち上がるオフィスビルの多くが、「Sクラス」と呼ばれる航空母艦のような威容を誇る巨大ビルたちであり、こうした外資系金融機関を受け入れるには十分な性能を備えている。
これらのビルにはオフィスのみならず住宅やホテル、商業施設や美術館、ホールなどが併設され、建物だけで一つの街を形成するようなビルが続々と誕生を予定している。東京のオフィスビルマーケットはこれから発生する膨大なオフィス需要にも十分応えて成長することが期待されているのだ。