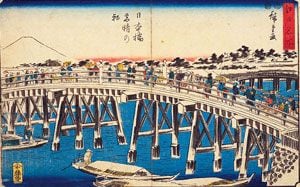学校の教科書は「時代」が変わると仕切り直しになってしまう。しかし現実の歴史は1本のタイムラインで今日までつながっている。江戸時代以降の400年を人口、経済、気温、身長の4つのデータから読み解く。第3回は「気温」について――。
※本稿は「プレジデント」(2018年2月12日号)の特集「仕事に役立つ『日本史』入門」の掲載記事を再編集したものです。
冷夏が招いた、江戸三大飢饉
地球の気温は暖かい時期と寒い時期を交互に繰り返しながら、大きなトレンドの中で変動しています。ざっくりとした時代ごとの寒暖を言うと、縄文時代は暖かく、弥生時代には寒くなり、平安時代にはまた温暖になり、江戸時代は再び寒くなりました(14世紀から19世紀半ばは「小氷期」と呼ばれます)。
もちろん平安時代にも底冷えのする寒い冬はありましたし、江戸時代にも猛暑の夏がありました。この気候区分は、数百年という長い時間軸で特徴づけたものであり、その前提で、江戸時代は「総じて寒かった」ということが言えます。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント