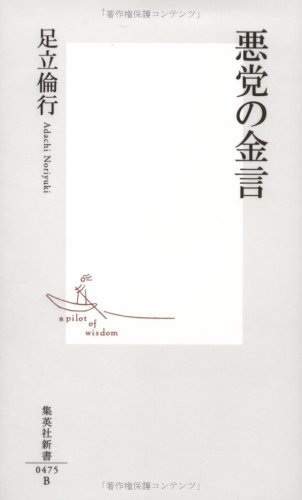30年前の新宿で味わった「インタビュー」の醍醐味

足立倫行●あだち・のりゆき 1948年、鳥取県境港市生まれ。早稲田大学政経学部中退。週刊誌記者を経てフリーに。著書に『日本海のイカ』『妖怪と歩く 評伝・水木しげる』など。
今から約30年前、夜更けの新宿で取材したある若者のことを、足立倫行さんは今もよく覚えている。
当時、「平凡パンチ」の記者だった20代の彼は、“眠らない街・新宿”をテーマとしたルポを準備していた。その取材で新宿中央公園を訪れたとき――。
「街のボウリング場で働いているという男女に会ったんです。聞けば男性のほうは東北出身で、上京後の苦労や楽しさを、書ききれないほど語ってくれた」

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(公文健太郎=撮影)