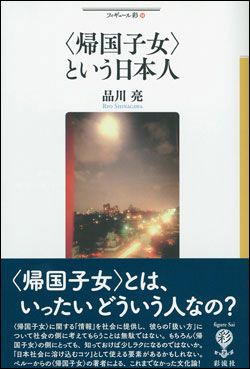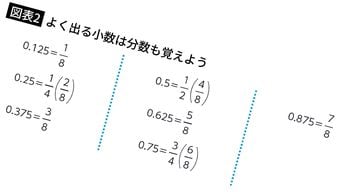※本記事は、『<帰国子女>という日本人』(彩流社)第5章「<帰国子女>という社会人」から引用抜粋したものです。
「ひとつだけあの人が心配しているのは......」とだいぶ長いあいだおしゃべりをしたあとで、打ち合わせ相手が付け加えました。
「海外生活が長いからかもしれないけど、あなたが言葉を字義どおり受け止めすぎるんじゃないかということなんだよね」
あの人というのはいわゆる「クライアント」のことで、わたしにそう話すのは「クライアント」とのあいだに立って、実際の「プロジェクト」を管理する立場にいた人です。この人とはその時点ですでに何年にも及ぶつきあいでしたが、そういうかたちでいっしょに仕事をするのははじめてでした。
「クライアント」と会ったのはたしか一度か二度で、わたしが「言葉を字義どおりに受け止め」る傾向を持っているのかどうか、その程度の時間をすごしただけでわかるのかなあとまずは感じました。だいたい、「言葉を字義どおりに受け止める傾向」とはなにをさしているのでしょうか。
<帰国子女>は人間関係の機微がわからない?
たしかに子どもの頃には、大人たちに「あとで」といわれるたびに、遅くても「今日中」、早ければ「1時間以内」くらいの意味に受け取って、毎回裏切られた気持ちになったものです。まさか、彼はそういう小学生的な気質のことを話していたのでしょうか。いくらなんでも10年以上の「社会人歴」を持つ30代後半になった人間として、それほど幼稚な思い違いはしません。
「あとで……」といわれたら、「その場の空気」と相手との関係性が許すかぎり、どのくらいあとの話なのかについて質問しておくという程度のノウハウは身についています。要するに、相手の人格や状況によって言葉の意味を解釈するという訓練はできているつもりでした。
それでも「クライアント」は、わたしがひとの言葉尻を捉えて言質をとったつもりになり、それを盾に「ムリ」を押し通そうとするような人間だと思ったのでしょうか。たしかにそういう人はいます。そういう面倒くさい連中とは仕事したくないという気持ちもわかります。
「そういう人間じゃないですよ」とひと言、口添えしてくれればすむことなのに……などとぼんやり考えながら、「そのご心配には及びませんとお伝えください」と応えました。