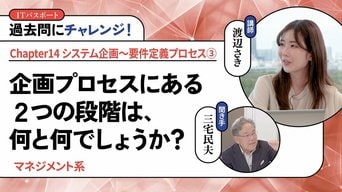NHKのテレビ小説「あさが来た」では、主人公が日本初の女子大学校の設立に奔走する場面が描かれていた。いつの時代も、先駆的な取り組みには、世間の偏見と資金集め等の困難が立ちはだかる。学校づくりはその最たるものだ。しかも本書の主役・小林りん氏が設立を目指したのは、学校教育法第1条に基づく正式な日本の高等学校でありながら、世界中から募集した生徒が寮生活を行い、英語で授業を行う日本初の全寮制インターナショナル校。前例がないだけに、設立の難しさは格別だ。

しかし小林氏は、その壁を持ち前の対人能力(ピープル・スキル)で乗り越えていく。夢だけでなく、理路整然と具体的なデータに基づいた計画を早口で語る彼女の説明を聞いた相手は、たいてい彼女に魅了され、協力的になってしまう(らしい)。軽井沢の1万坪の高級別荘地を、わずか1億円で購入したいと持ちかけた話が冒頭に登場する。本来なら無理な金額だが、心を動かされた不動産会社の担当者がありえないレベルの協力を行い、長期賃貸の仕組みを使うことで実現してしまう。
どうやったら、彼女のような情熱と行動力を備えることができるのか。本書の著者は、5年に及ぶ彼女への長期取材を経て、その解を導き出す。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント